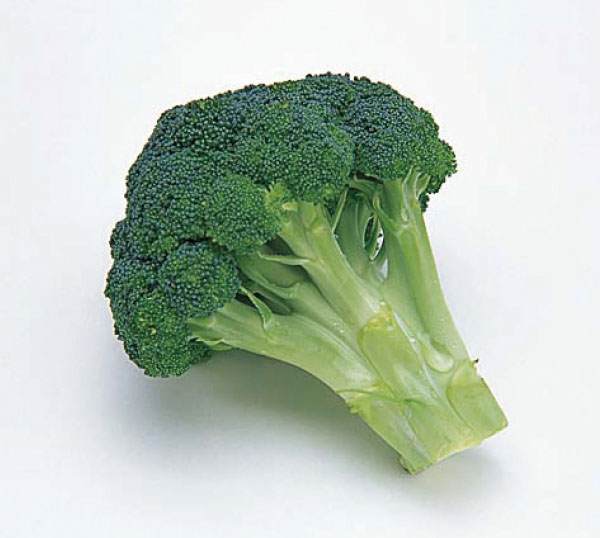クチーナ通信 危うしイタリア台所事情
主婦のルチアさんは最近マクロバイオティック(菜食や自然食による長寿・健康法)の本を買ってみたが、分からないレシピがあるので私に教えてほしいと言う。見ると、ノリやコンブなどの記述がある。
「これは日本で食用とされている海藻で…」と言い終わらないうちに彼女は顔をしかめ、「ああそうなの、海藻ねェ…どうせ売っている所も知らないし、ならやめるわ。私たちには消化が悪いって言うし…」。生まれてこのかた外国料理を食べたことのない彼女にとって、食用の海藻というのは理解を超えたものだったらしい。
この分では彼女のダイエット計画は延期になりそうだ。
これまでイタリア人の総体的な健康はいわゆる地中海式食生活によって守られてきたと言えるが、これは彼らが栄養学のエキスパートだったからでは決してない。例えば、私たちが小学校から教わり、常識として生活に浸透している栄養学の話がここでも通用すると思うのは大きな間違いだ。
「コメ・パスタ・パンは炭水化物」「砂糖のとり過ぎは糖尿病になる」「緑黄色野菜は一日に三○○グラムはとる」-こういった話をしても大部分の人はフーンと言って聞きはするが、いまの生活に取り入れる気はあまりない。
オリーブオイル、野菜、穀物、魚を中心とした食生活は確かにおいしいし身体にもいい。これまでこうした食生活が保たれてきた訳の一つは、彼らの食に対する「超」がつくほどの保守性にある。
イタリア人は外国に出掛けた時、その国の料理の賞味よりも先にイタリア料理店を捜し回るというが、国内でも事情は同じ。故郷を離れた人は「ここにはうまいものがない」といって嘆くほどで、自分が食べて育ったもの以外になじみにくい土壌があった。
しかし時代は変わり、例えば昔はなかなか食べられないご馳走だった牛フィレなどの高級肉も、そう手の届かない値段ではなくなった。そうなると栄養バランスなどは元より念頭にないため、パスタとメーンディッシュで満足したら野菜は食べずに済ませてしまう、という事態になりがちなのだ。
いまや都会の若者や子供には、ファーストフードのハンバーガーショップはカッコイイ食事場所として受け入れられつつあるし、遅ればせながらせまりつつある“食の欧米化”に、いまのところイタリア人はほとんど無防備に見える。
最近になってようやく日々の食事とは違う“健康を意識した”食生活というものに少しずつ関心が高まってはきたが、浸透度はまだ浅いのが現状だ。いまはまだ冒頭のルチアさんのように、新しい食文化をこわごわ覗いてみるといった段階のようだ。
かつての日本が進んで来た道をなぞっているようで歯がゆい気もするが、自国の食物の優れた点を違った角度から見直す動きが少しでも活発になっていくことを願わずにはいられない。
とりあえずは、ルチアさんのダイエットが成功するまで根気よく付き合っていこうと思っている。
(イタリア・トリノで料理修業中 合田達子)
イタリアの民間療法
☆消化不良に…CANARINO
(カナリーノ)
【材料】無農薬のレモン皮1個分、ローリエ1~2枚
【作り方】小なべに湯をわかし、レモンの皮1個分とローリエを加え5分ほど煮立てる。色が十分出たらカップに注ぎ、好みで蜂密などを加えて飲む。
☆風邪の予防に…VINO COTTO
(ヴィーノコット)
【材料】赤ワイン2カップ、クローブ1本、シナモン小1片、無農薬のレモン皮1個分
【作り方】小なべに赤ワイン、レモン皮、クローブとシナモンを加え、10分ほど煮立てる。お好みによって砂糖を加え、熱いうちに飲む。