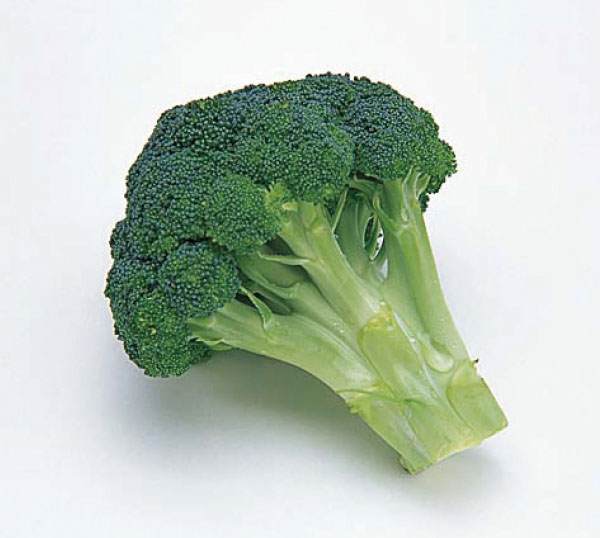ネパール流医食同源のすすめ「スパイシーだが辛くない」
北は中国、東西南をインドと接するネパール。東西約八〇〇km、南北約二〇〇kmと細長い地形で、国内標高差なんと約八〇〇〇m。エベレストをはじめ高山が国の四方を取り囲む。山岳地帯ではジャガイモやソバ粉などを主食として食べるが、カトマンズなどの盆地ではコメを主食とする。
ネパールの一般的な食事“ダルバート”はご飯(バート)に野菜料理(タルカリ)、豆のスープ(ダル)が中心。
味はスパイスが効いているものの、インド料理ほど辛くない。「ネパールではあまり激しい辛味は、品が悪いとされます。自分の好みで後から唐辛子をふりかけたり、別のスパイスを噛みながら食べたりして辛さを調節します」。
ご飯を炊くのもスパイスで。マテマさんが教えてくれた“ネパール風ピラフ”は、水にローリエ・カルダモン・シナモンスティックを入れ一時間ほど煮込んだスープでコメを炊く(コメは細長いインディカ種を使用、水で研いだあとギーというバターであらかじめ炒めておく)。ふんわりやさしい香りが、おかずの味を引き立てる。
スパイス使いが上手なネパールでも、特筆すべきなのはサンショウだ。野菜と和えて「アチャール」という漬物を作ったり、また薬として、腹痛止め・吐き気止め・解毒・咳止め・酔い止め・ヒル防止に利用するなど、あらゆる場面でとても活躍する。現在ネパールでは薬局で買う薬が主流だが、いまだ遠出や山歩きの時は、この実をポケットに携帯する人が多い。
面白いのはこのネパールのサンショウ(ティムール)は、同じ名前でも日本の「山椒」とは違う種で、正確には中国原産の「花椒(ホワジャオ)」を指す。
両者の違いは『大きさ』(山椒の方が大きい)、『色』(山椒は緑、花椒は赤っぽい)、そして『味』(山椒の方が辛みも香りも強く、舌がしびれてしまうほど)。山椒は日本でしかとれない稀少品のため、価格も三倍ほど高い。昔から病除けとされ、正月の「お屠蘇」にも入れられる。
一方、花椒は、中華調味料「花椒塩」「五香粉」の材料として、揚げものやあんかけ料理など広く使われる。寒いとき保温剤として用いたり、たくさんの種実をつけるので「子孫繁栄」を象徴するめでたい木の実ともいわれる。
(取材協力=ネパール王国大使館、ヒマラヤ観光開発(株)、東京ガス新宿ショールーム)