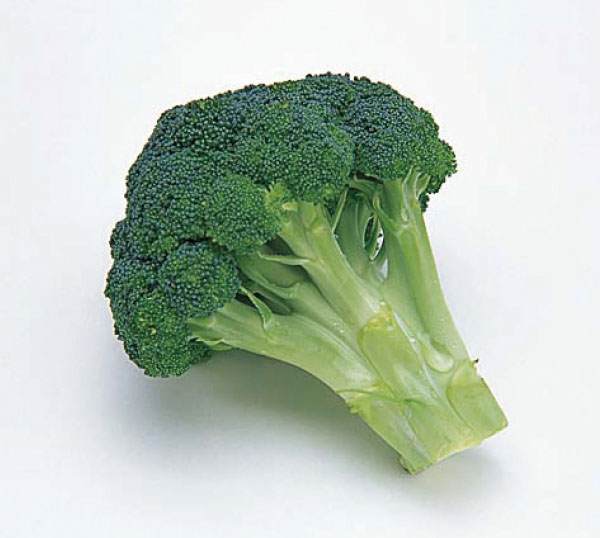ようこそ医薬・バイオ室へ、「人間の設計図」ヒトゲノム解読
二〇〇〇年6月26日、クリントン米大統領はホワイトハウスで記者会見を開き、米バイオベンチャー企業のセレーラ・ジェノミックス社と、日米欧の国際ヒトゲノム計画チームのそれぞれが、「人間の設計図」であるヒトゲノム(全遺伝情報)の解読作業をほぼ終えたと発表した。ブレア英首相も衛星回線で会見に参加し、「人類の財産」と絶賛した。
同日、日本でも理化学研究所の榊プロジェクトディレクターと慶応大の清水教授が科技庁を訪れ、中曽根長官に解読の終了を報告した。
ちなみに、今回発表されたのは概要版で、詳細版は二〇〇三年に発表予定である。概要版で国際チームが解読したのはゲノムの八六・八%で、その寄与率は米が六七%、英が二二%、日本が七%、その他が独仏などであった。
各局のテレビがこの模様を取り上げて、私なんぞは仕事柄「やっとこの日が来たか」と感慨深かったのだが、「ヒトゲノムって何?」と思った人も多いと思う。確かに、あの月に人類が立ったアポロ計画に匹敵する巨大科学プロジェクトといわれても、それほど素人受けするニュースではなく、「だから何なの」と聞かれると一言で説明しづらい。
とりあえず、「ゲノム」から説明すると、ヒトの身体は約六〇兆個の細胞からできていて、その細胞の一つひとつの中に核がある。核の中には紐のような染色体というものがあって(ヒトの場合は四六本)、その染色体の一本一本は細い糸のようなDNAがきれいに折り畳まれていて、一個の細胞中に入っているDNAの長さは約二メートルといわれている。このDNAが遺伝情報を担っているわけなのだが、それはA(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、T(チミン)という四つの塩基が階段状につながったもので、遺伝情報というのはこの四文字のみが途切れなくただ並んでいる暗号文のようなものなのである。
で、「ヒトゲノム」というのは、ヒト細胞の核の中にある三〇億文字の全遺伝情報のことで、その解読とは、先のAGCTの四文字がどんな順番で並んでいるかを調べることである。三〇億文字といってもピンとこないと思うが、『NHKスペシャル遺伝子』によると、「百科事典にして七〇〇冊分の文字数」というから、とんでもない膨大な数なのである。
この三〇億文字の一部が遺伝子で、ヒトの場合、一〇万個の遺伝子がこの中に隠れている。大体一遺伝子当たりの文字数は平均で二〇〇〇文字程度であるので、一〇万個の遺伝子とすると二億文字くらいしか使われていないことになる。つまり、ヒトゲノムの中には遺伝子ではないDNAが二八億文字も存在しているわけで、どこが遺伝子なのか探ることが意外に難しいのである。
しかも、つい最近の科学雑誌に、これまで一〇万個といわれていたヒトの遺伝子数が実は三万個という発表と、一二万個という発表が同時に掲載された。最新の情報処理技術を駆使しても、遺伝子の数さえ分からない状態なので、今後どこに遺伝子があり、その遺伝子がいつ働き、何をするタンパク質に翻訳されるかを解明するのが、全世界の競争となる。アポロ計画がコンピューターや新素材の進歩に波及効果をもたらしたように、ゲノム計画も病気のしくみの解明を通じて医薬品・医療に革新をもたらすだけでなく、進化論や生命観を大きく変える可能性を持っている。
ところで、このゲノム計画は、日米欧の国際チームが一九九〇年から始めたものであったが、昨年ベンター博士が作った冒頭のセレーラ社は、約一〇〇〇億円を投じて最新の解読装置三〇〇台とスーパーコンピューターを駆使して、国際チームが一〇年かかった仕事をわずか九カ月で追い越してしまったのである。
そのため、ヒトの遺伝情報を「公共財」としてインターネットで公開していた国際チームとセレーラ社との間で大きな軋轢を生んでいたが、結局、米政府や学界が和解を働きかけ、今回セレーラ社と国際チームは一時的でも手打ちをした形で、ホワイトハウスに招かれている。
一方、我が国では、衆議院選挙直後でそれどころでなかったのか、政府関係者のコメントは特に報道されていない。
(新エネルギー・産業技術総合開発機構 高橋 清)