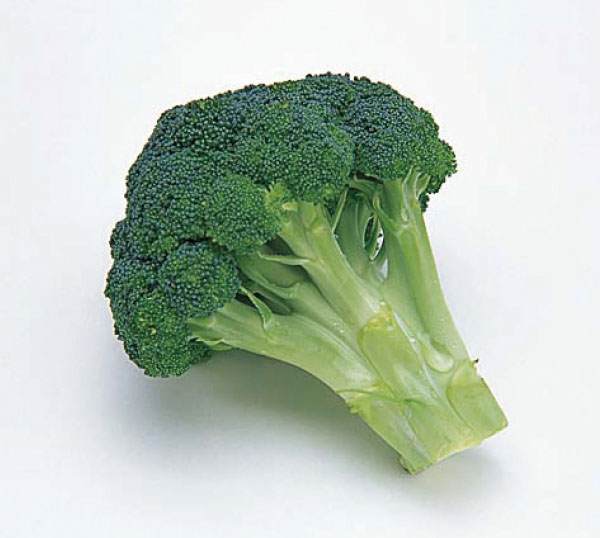ようこそ医薬・バイオ室へ:食べるワクチン、実用化なるか
いま話題の新しい機能性食品として「食べるワクチン」がある。今年の8月に大阪医科大学と協同乳業が、胃がんや胃潰瘍の原因といわれるピロリ菌に効くタマゴの開発に成功したと発表し、同時に埼玉のイセ食品からそのタマゴが発売された。
そもそも、ピロリ菌が胃の中の強い酸性下でも生きられるのは、自身がウレアーゼという酵素を出して、その酵素で生産されるアンモニアによって胃酸を中和しているためである。今回開発されたタマゴは、卵黄の中にウレアーゼの反応を阻害してアンモニアを発生させない抗体が入っているという。その生産方法は、ピロリ菌の抗原物質を「エサ」として混合、鶏に与え、卵黄に抗原物質に対する抗体を集めるというもの。ただエサに抗原を混ぜただけなので、遺伝子組み換えした鶏やタマゴではないところがミソである。
ところで、発展地上国の二〇%の子供が予防接種を受けないために、ジフテリア、百日咳、小児麻痺、破傷風、結核などによって年間二〇〇万人も死亡しているといわれる。そこで、一九九〇年代の初めに、米国テキサス大学のアーンツェン博士が、開発途上国の子供に高価なワクチンを行き渡らせるにはどうしたらよいかと考えていた時に、シンガポールで、子供にバナナを与えている母親を見て「食べるワクチン」を思いついたという。
つまり、植物を遺伝子組み換えで改造し、食用部分にワクチンを作らせれば安価で、それぞれの地域にあった食べ物なら輸送の必要もなく、しかも食べることによって接種できるので注射器なども不要になる。大変高尚な目的のもと、それ以降、世界中の科学者がバナナやジャガイモなどに、はしかや病原性大腸菌などの病原菌の一部の抗原遺伝子を遺伝子組み換えで入れて、そのバナナなどを食べるとその病原菌に対する抗体ができて感染しにくくなるという「食べるワクチン」を開発し始めた。
先のアーンツェン博士は、急性胃腸炎のウイルスと大腸菌の抗原をつくるジャガイモを開発し、そのイモを生のままで被験者に食べさせたところ、免疫反応を刺激することに成功した。生のままで食べさせたのは、加熱調理して抗原がダメージを受ける可能性を恐れたためだったが、ボランティアはさぞ食べにくかったことだろう。しかし、この実験により、ワクチンは効力を保ったまま消化器を経由して血液中に入ることが分かった。
また、米コーネル大ボイス・トンプソン研究所(ニューヨーク州)の温室では、B型肝炎ウイルスや病原性大腸菌のワクチンが含まれているバナナが育てられている。ただし、食べた抗原の多くは胃の中で消化されるため、食品中の抗原の量がさらに二〇~五〇倍は必要だという。バナナと並行して、生育が早く育種の歴史もあるポテトやトマトで研究が続けられている。
しかしながら、これらは前述の「タマゴ」と違って遺伝子組み換え食品(GM作物)であるため、消費者からの反対は非常に根強い。家畜向けの「食べるワクチン」を開発しているプロディジーン社(米)では、ベンチャーキャピタルの出資がピタリと止まり、アクシス・ジェネティックス社(英)の場合は、B型肝炎の「食べるワクチン」であるジャガイモを開発したものの、臨床実験の費用を調達できず、経営が破綻した。欧州の激しいGM作物への反対運動に、投資家がすっかりおじけづいてしまったためである。
「食べるワクチン」の実用化に向けた技術的な障害はまだ数多く存在するが、最大の関門はGM食品全般に対する消費者の不信感のようである。
((株)ジャパンエナジー医薬・バイオ事業部 高橋清)