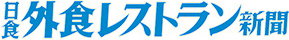シェフと60分 ひらまつ製パン長・立川善博氏 自然酵母の長時間熟成にこだわる
一一年間のホテルでのパン作りから一転、現在の職場に移り、「自分が本当においしいと思うパンを作れる環境にある」のに感謝する。
ホテルでのパン作りは、大量生産システム。味は二の次、一〇〇点満点中五〇~六〇点ならよしとされていた。職場で一番レベルの低い者に合わせてのパン作りだった。安全第一、極端にいいものを作る必要もなかったともいう。
勤務時間の八時間内で数をこなすノルマ制、また、いろいろな添加物を使うことで、簡単にパンが作れる風潮に「本来のパン作りからズレているのでは」と常日頃、疑問を抱いていた。
自分で店をやるしかないとまで思い詰めていたところに、現職場の話が持ち上がり、「おいしいパン作り」に共鳴、自身を賭けてみることにした。
パンは生き物。真心をもって接しなければいけない。作り手の気持ちがそのまま入るというわけだ。
「パン屋は、農夫と同じ」朝9時に働き出し、夕方5時に仕事終了では収穫は得られない。「陽が昇ると同時に仕事を始め、陽が沈んだら仕事を終える--、雨でも嵐でも農作業をしなくてはいけない」。パン屋も同じ、「おいしく、健康的なものを食べてもらおうと思ったら、気持ちを込めて作業をしなければいけません」。
パン業界が速成法で早く発酵させる方向にあるなか、「自分が良いと思うものを作りたいから」と、あえて長時間発酵に挑戦する。また、最後の最後まで見届けるため、睡眠を四時間としパンとともに寝起きもする。
日本の素晴らしい製粉技術で精製された小麦粉では、気を使うこともないが、フランス、カナダの自然の恵みをそのまま生かした小麦粉はそうはいかない。
目が離せない。常に変化を見届け手当てをしないと、パンの表情が変わる。
「医者と同じ。粉の状態に合わせ、厳しくしたりやさしくしたり、まるで赤ん坊に接しているようなものです」
日本の粉を使えば、こうした煩わしさから開放されるわけだが、むしろ味のある小麦粉をどう生かすかに奮闘し、喜びを見出しているほどだ。
初めて手に触れた時、難しいと思ったが、仕込むうちに少しずつ相手がわかり、「もっと知りたい気持ちでいっぱい」、今では、これを生かしたパンメニューのアイデアが限りなく湧き上がる。
「粉の配合はどこのパン屋も同じ。ただ作り方が違う。テクニック的なものではなく、手の皮が剥けるほどに、絶対に良いものにしようという意気込みが、パンを変えていく」という。
自身は、自然酵母の考えでパン作りをしているため、長時間発酵をとっている。八時間は寝かし、夜中の1時ごろから成型、焼成を繰り返し、明け方5時ごろに焼き上げ、商品として店頭に並べる。
昼ごろ、翌日分の仕込みを始め、分割を終えて冷蔵庫に入れて寝かす。「これがうちのパンの生き方です。私の生活も同じサイクル」というほど打ち込むだけに、焼き上がった時、パンの表情を見るのに不安と期待が交錯する。
パン作りの原点として、後進には口を酸っぱくしていうことがある。
「ご飯を食べる時、いただきますという感謝の気持ち、また、母親がご飯を炊く時と同じで、おいしいものを作って喜んでもらおうとする気持ち」これさえ持ち合わせれば、パン作りはOKと。
「今ではこうした気持ちを持つ者も少なくなってきた」と嘆きながらも、一人ひとりにパン作りを通して根気よく教えていく。
毎日丹念に作り上げるパンが売れていくのは、「食べ手に受け入れられたから」と受け止める。
今の段階では、自分自身にとり最低ランクだが、本当のパンの食べ方を教え、それが広まっていけば「近い将来には、私自身も食べ手もレベルアップする」と信じる。
また、自身と同じ価値観を持った仲間、パン食文化を真剣に考える仲間を増やしていきたいと訴える。
オープンキッチンで働くのは初めての体験だ。
今までは、自分たちが作ったものが、どう売られ、どう食べられているか知る由もなかった。
「見えるだけに、作り手、食べ手ともに真剣勝負です」
客が食べる姿に、一種の気迫さえ感じられる。
各人、自分が作ったものに名前を記して自らの気持ちのあらわれとし、また、できるだけ客席に出向き、客との会話を楽しむようにもする。
なかには、パンの中のクルミはどこから入れたものか、自分の知り合いに巨峰のいいものを作っているなどの情報も飛び交う。
「料理人にはこうしたチャンスはあるが、パン職人にはなかったこと。お客と直に触れられる状況に感謝したい」と、新しい環境に戸惑いは微塵も感じられない。
他のスタッフも、パン作りを自分で選んだ道と燃えており、彼らが同じように一六~一七時間も働く姿を見ると、「何とかしてチャンスを与えたいと」とリーダーとしての意気込みをみせる。
まさにパンとともに明け、パンとともに暮れる毎日だ。
昭和41年、神奈川県生まれ。祖父はパン屋だった。戦争のため小麦粉が手に入らず店をたたんだと聞いていたが、自らがパン職人を目指すとは思わなかったという。
二四歳ごろ、何の苦痛もなくガムシャラにパン作りに励む自分自身に気付く。餅は餅屋の子、自然の成り行きかもしれない。
ホテル小田急センチュリーハイアットの製パン課を振り出しに、横浜プリンスホテル、幕張プリンスホテルなどホテル系に勤務後、現在に至る。
家族のもとから通勤したのでは時間がロスになると、職場でパンとともに寝起きし、時間があるとおいしいパンを求めて食べ歩く、まさにパン三昧の日々である。
文 上田喜子
カメラ 岡安秀一