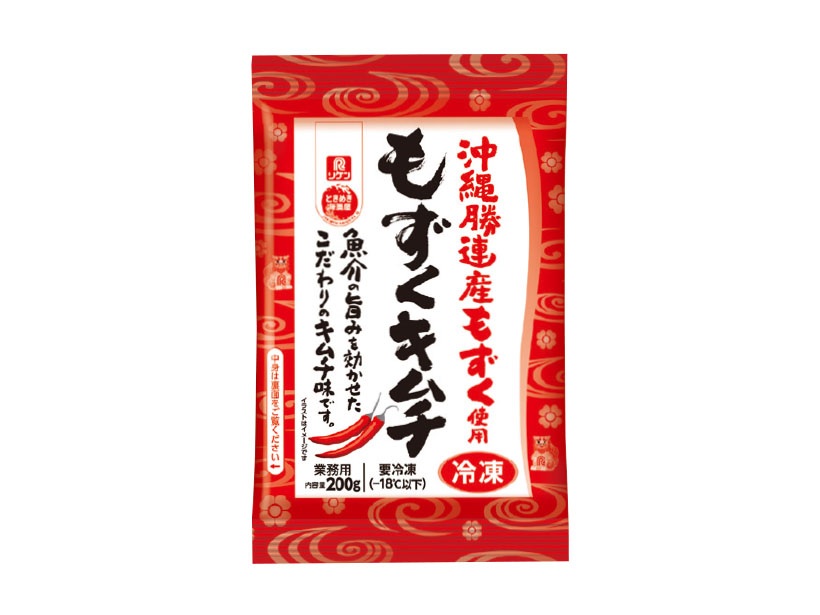シェフと60分:「新橋亭」総調理長・田中喬氏
「料理人として奮い立たせてくれたのはまかない」と言い切る田中調理長。
志を抱き、「赤坂山王飯店」に入社。三年の歳月がたったころ、師となる五人の中国人コックのまかない番を務める。
当時の日本人コックは約三九人。うち同期は五人だったが、次々と落伍していき、残ったのは田中さんただ一人。
「まかないといっても同僚ではなく、舌の肥えた中国人コック。知恵と腕の限りを尽くして作ったが、手つかずで皆さん食べなさいと突き返されたときの悔しさ」
しかし、ここでひるむ若者ではない。「レシピのない時代。先輩が作る料理を見、鍋に残ったソースをなめ、すべて目と舌の五感で覚えるしかない」と自らに言い聞かせ、チャンスをとらえては師匠の後を付いて回る。
鍋を洗って覚えた味、中国料理には欠かせない合わせ調味料も、一年がかりで盗み見して会得。
伝説的にいわれる彼らの魔法の調味料は、実は甘草とクコの実を発酵、乾燥させ粉末にしたもののほか、薬膳に使う五味など一七~一八種の粉末を合わせたものらしかった。
田中さん自身、現在は約一四種を合わせたオリジナル合わせ調味料を使っている。
「料理をやるなら一流店で修業しようと心に決めた地が新橋。長い道のりではあったが、今再び新橋に舞い戻ってきた。この道筋は、まさに運命づけられていたのかもしれない」と語る口調は感慨深げ。
思い起こせば、「山王飯店」などを経営する呉三宝、四宝、東宝の三兄弟が幾度となく足を運び説得、中国の故事にある「三顧の礼」を尽くし、「築地新橋亭」立ち上げの調理長として迎えられたのが昭和50年。三三歳のことである。
「ただし条件を付けました。すでに四〇店舗を展開していた新橋亭○○店と区別し、私流の色を出すため築地新橋亭にしてくれと」
人通りの少ない築地割烹街の中にあり、当初売上げは月商三〇〇~四〇〇万円。ここで手をこまねいてはいけないと新たな戦略を仕掛ける。
料理は、三人の中国人厨師から受け継ぐ上海料理を柱に、日本人好みにアレンジした田中流上海料理。
これに暑い夏、寒い冬にはどんな料理がいいのかといった単純な発想から、当時少なかった薬膳料理を打ち出す。先人はいない。薬膳専門店に通っての研修と知識として専門書を読みあさってのスタートを切る。
基本は素材の持っている効能と四季の素材を生かし、熱・温・平・涼・冷の五感を組み合わせた料理。
ほかにミニ満漢全席がある。本来なら四十数品目だが、発想を切り替えて日本人の胃袋に合わせ一二品くらいに抑える。
価格と量目、ミニの語感がうけたのか多くの客の足を運ばせ、月商四〇〇〇万円と一〇倍もの伸長となった。
「独自性を出さなかったらやっていけない。お客が三回通っても気がつかない場所にあったから」
持ち前の進取の気質と大胆な行動力は、現在の新橋に移ってからも衰えることはない。
四五〇席、ゆったり座って二八〇席。一日約二〇〇人の客数で年商七~八億円を維持する新橋亭。
「新橋亭をここまでにしたのは私と自負しているが、恩義も感じている」だけに、店名に対する思いは人一倍。
かつては四〇店舗を展開していたが、思い切って直営の六店舗に絞り込む。地域に根ざした店舗をと毎月チーフが集い、各店の点検・検討を行う。問題点があれば現地で徹底検証する。
「各店は独立独歩。二年もすれば結果は出る。昨年は一人解雇した。今は料理を作ればよい時代ではない。指導力、経営力も求められる」と語る表情は厳しい。
ターゲットの客層ランクを常に七~八に置く。景気の良しあしで上からも下からも吸収できるとの計算があるからだ。
「今後、従来の招待客、宴会客に加え、汐留開発の流れで一般消費者の需要喚起を狙いたい。また景気の影響で昼の接待が増えはじめており、これをどう取り込むかも一つの課題です」
文 上田喜子
カメラ 岡安秀一
◇私の愛用食材
花のキンモクセイを思わせる香ぐわしさとまろやかな味わいをもつという「香辣醤」。
「すでに定着している人気の高いXO醤を超える新しい調味料」と絶賛してやまない田中調理長。
「今までは辣醤を油で焼いて塩分を飛ばし、辛みと風味をバランスよくブレンドして使っていた」が、この香辣醤は、ほどよくブレンドされている調味料。
辣醤ほどのストレートな辛みがなく、辛みの中にもほのかな甘みが感じられる。
オードブルとして生ゆば包みのつけだれに、またミル貝との炒め合わせにしたり、若者向けメニューの牛肉と黒コショウ合わせに使ったり、さまざまな隠し味として重宝しているという。
XO醤でも辣醤でもない「香辣醤」は、二一世紀の新しい調味料として確実に広まると確信する田中調理長である。
◇プロフィル
昭和17年山口県生まれ。高校卒業後、日新製鋼に入社、設計部門を担当するが、上司と折り合いが悪く退職。新天地を求めて上京。東京では親戚、知人もいなく、住み込み可の張り紙に引かれ、新橋駅前の「天津飯店」を仮の生活の場とする。
ここで見た実力主義の世界に引かれ、自らをかけるべく開店と同時に赤坂山王飯店に入社。以後、38年の「原宿皇家飯店」、41年「銀座大飯店」、44年には板長として「自由が丘南国飯店」に勤務。また48年は銀座「青綺門」の調理長、50年「築地新橋亭」の調理長、平成元年には「新橋亭新館」調理長として、常に開店立ち上げの料理長として赴任している。平成4年に「新橋亭」総調理長となる。
・所在地/東京都港区新橋2-4-2
・電話/03・3580・2211