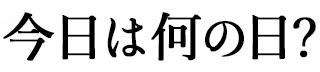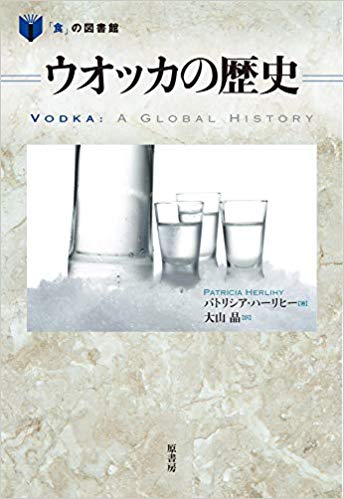10月19日。今日は日ソ国交回復の日
1956年10月19日、モスクワのクレムリンで、「日ソ国交回復の共同宣言(日ソ共同宣言)」が調印された。
ロシアの酒といえばウオッカ。しかし現代、ウォッカを最も消費しているのは……
ウオッカの起源として、12世紀にロシアにすでにあったという説と11世紀にポーランドに存在したという説の2説がある。しかし、記録としてはモスクワ公国(13世紀~16世紀)の記録には、ロシアの農民が飲んでいたことが記載されていることから、12世紀前後には東ヨーロッパで飲まれていたと考えられる。 初めは蜂蜜の酒(ミード)やライ麦のビールを蒸溜していたと考えられる。これら蒸留酒は生命の水を意味するジーズナヤ・ ヴァダー(Zhiznennia Voda)とよばれていたが、やがて水を意味するVodaの部分のみになり、16世紀には愛称形のVodkaが使われるようになった。原料は17 世紀ごろにはライ麦が用いられていたが、18世紀にはジャガイモやトウモロコシも使われるようになった。当時は単式蒸溜であったこともあり、雑味が多い酒であったと考えられる。大きな転機はサンクトペテルブルグの薬剤師、アンドレイアルバーノフが炭の吸着性を発見し、その後ピョートル・スミノフが木炭にウオッカを通して精製する技術を完成させたことである。19世紀になると連続式蒸溜器が 導入され、よりクリアな原酒の製造が可能になり、ウオッカはロシア中に広く愛され、その酒税は政府収入の30%に達したという。ウオッカが世界に広まるきっかけとなったのは、1917年のロシア革命により、フランスに亡命したウラジーミル・スミノフがその地でウオッカの製造を始めたことにある。第二次世界大戦を契機にウオッカは少しずつ世界に広まり、1950年代にいたってその無色で軽い香味が アメリカで爆発的な人気をよび起こした。1955年から70年におよび15年間にアメリカにおけるウオッカの消費量は約18万klと7倍となり、以降世界一の消費量を誇っている。わが国では大手メーカーを中心としてウオッカが生産されている。2012年の輸入量は約3,500klであった。
(日本食糧新聞社『食品産業事典 第九版』(引用箇所の著者:東京農業大学 徳岡昌文))