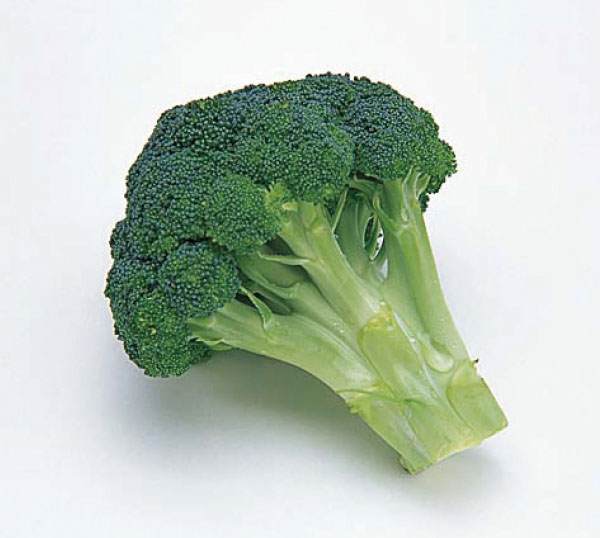だから素敵! あの人のヘルシートーク:落語家・内科医・立川らく朝さん
「社会人やりながら落語家やってます」という異色の落語家、立川らく朝さん。昨年、四六歳で立川志らく門下に正式に弟子入りし、前座として高座を務めるなどプロの落語家として活動する一方、企業の産業医としての仕事やエイズ対策の講演・企業研修・コラム執筆なども精力的にこなす毎日を送っている。
生まれて初めて落語を演ったのは、高校三年の文化祭。当時から落語を見るのが好きで、新宿の末広亭によく通いました。大学時代は自ら落語研究会を創設。社会人になってからもしばらくは落研OBで年一回寄席を開いていましたが、会場にしていた上野の本牧亭がなくなりOB寄席も自然消滅。
それから約一〇年は落語との縁も途絶えたものの、酔っぱらうと「俺はなぜ落語をやっていないんだ」と、やりたいことを成し得ていない自分を責めるもう一人の自分が現れて、「落語やれよ」としきりに耳元でささやくようになったんです。
そんな折、立川志らく師匠の主催する勉強会「らく塾」に出合い、師匠の落語理論を聞いたり実技をしたりする、月一回の落語好きの集まりに出席するようになりました。そして一年後、志らく師匠に弟子として入門を申し込んだんです。
とはいえ、もはやまともに前座修業ができる環境ではない。カミさんも子供もいて、しかも年齢が四四歳という中年のおじさんです。「とても無理ですよ」「そこを何とか」と食い下がって、ついに「客分の弟子」として落語を教えていただけることになったんです。プライベートレッスンということで月謝を払うかわりに、前座修業は免除。ただし立川の落語会だからといって高座にあがれる保証はないという約束でした。
「客分の弟子」だなんて、師弟関係の厳しい落語会で滅多に許されることではなく、すべて志らく師匠の厚意によるもの。以来二年近く、楽屋やら客席やらホールのベンチやら、時には高座やらと、落語会場の周辺に身を置かせてもらいました。その間にネタ数は五〇を越え、師匠から「そろそろ“二つ目”に」といわれ、立川企画の社長からも「もしその気があるなら本格的にやってみないか」というお誘いをいただいた。
「好きな道だ。やれるところまでやりたい気持ちは山々なれど、本格的なプロとなると、仕事と両立できるかしら。いくら何でもキツすぎるよなぁ」と三ヵ月悩み、返事ができません。ところが、そんなある日、師匠と立ち話で「あ、そういえば、あの話どうするの?」といわれ、反射的に「お願いします」と言っていたんです。人生は人知では計れない可能性を秘めているもの。なまじ小賢しい決定をするより、こうなったら衝動に身を任せてみるのも一つの選択かなぁと。四六歳の春でした。
そして、昨年3月、晴れてAコースの前座となりました。入門当時の私の語り口が志ん朝師匠に似ていたことから、志らく師匠の「らく」と志ん朝師匠の「朝」で「らく朝」という素晴らしい名前をいただきました。
ネタづくりは、大体本番直前。考えに考えてこねくり回して作ったものより、すっとひらめいたものの方がうまくいくんです。ひらめくのは喫茶店やトイレの中。実際ブツブツ声を出し、身振り手振りなどしながら作り上げていきます。一見したら「アブナイ人」と思われてしまうかもしれませんね(笑)。
創作落語は古典落語をベースにオリジナルの健康ネタを加えたもの。テーマは「がん」「骨粗鬆症」「ボケ」「生活習慣病」、次は「糖尿病」を用意する予定です。
落語ですから時代背景は江戸時代。でも困ったことに、当時にはいまのような生活習慣病などないんですね。野菜と雑穀中心の食事で、よく働き運動も十分だとくれば、高コレステロール血症の人など稀。そこで私流の味付けで患者を登場させて話につなげていくわけです。
大変なのは頭の切り替えと時間のやりくりです。「落語」から「医者」の頭へ切り替えるのは簡単ですが、「医者」から「落語」へ切り替えてテンションを高めるには、倍以上の力が必要です。寄席のある日は、午後4時ごろまで医者の仕事をし、仕度をして5時に会場入り、7時に舞台が始まって、終わると打ち上げ、師匠たちにお茶やビールを運んだり後片付けをしたりして、出るのは11時過ぎ。その間に稽古をして、連載ものの原稿を書いて、と毎日あっという間に過ぎていきます。その時その時、集中力をもって取り組み、ガラッと頭を切り替える。そこをうまくやるには、体力も必要。疲れをためたままにしておくと、ダメですね。
実は正座が得意じゃないんですよ。法事などでは一〇分でシビレが切れちゃう。でも不思議。落語の時は二時間でも平気で座っていられるんです。むろん落語を演るときはべったり座り込むのでなく、結構激しくせわしなく動き回っていることもあります。一席やればもう汗だく。あごからポタポタ滴る汗を拭いながら話し続けるんです。体力が勝負です。
落語家はなぜか、長寿な方が多い。結構ハードな体力仕事だし、頭を使って腹から大きな声を出す、というのがよろしいんでしょうかね。私自身は医者の不養生っていう通りで、健康に気を使ったことは特にしていませんが、よく寝るようにはしています。
咳がひどく声も出なかった時も、舞台へ上がったらぴたっと止まり声も出た。人間の身体ってつくづくすごいなぁと思いましたね。以来、体力に自信もつきました。
四〇代の挑戦といっても、仮に七〇歳まで落語をやり続けるとしたら、あと二四年。そういう長い目でみれば、前座修業の期間というのはほんの数年間のこと。可能性を広げていきたいですね。
◆プロフィル
たてかわらくちょう 本名、福沢恒利。昭和29年、長野県飯田市出身。昭和54年、杏林大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部内科学教室へ入局。主として生活習慣病、動脈硬化症及び予防医学の臨床と研究に従事。平成2年、同学部老年科学教室に移籍、3年、慶応健康相談センター(人間ドック)医長兼務。4年、同大辞任。メディカルサポート研究所設立、現在同代表。10年、44歳で立川志らく門下に客分の弟子として入門。勉強会「立川らく朝一人会」を毎月開催。12年、同門下に正式な弟子として改めて入門、前座としてプロの落語家活動を開始。
●主な著書=『外国で安心して医者にかかれる本』(主婦と生活社)、『怪我と病気の英会話』(新星出版社)、『熱く語る・企業のエイズ対策』(エフエー出版)、『AIDS職場での取り組みQ&A』(東京都)など
●連載コラム=テレビ朝日データ放送(全国ネット)「ドクター福沢の見える救急箱」、医事通信「健康いろはカルタ」など健康講話を連載中。また、ホームページ「ご近所のお医者さん情報」は、医院や病院を専門分野など詳細な条件で検索できる、超人気サイト。
▽立川らく朝ホームページ
http://www.246.ne.jp/~rakuchou/
◆お知らせ
『第5回立川らく朝のちょっと身体にいい落語会』
健康にテーマを絞ったユニークな落語会。今回は『糖尿病をテーマに新古典を一席』。糖尿病が気になる人、親族に糖尿病の多い人におすすめ。
日時=平成13年5月28日(月)開場18:30 開演19:00~20:45
場所=東京・六本木 不動院(地下鉄「六本木駅」下車 徒歩5分)
問い合わせ=メディカルサポート研究所 03・3238・7845
入場料=1000円(当日会場で)