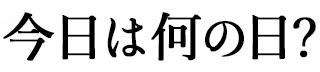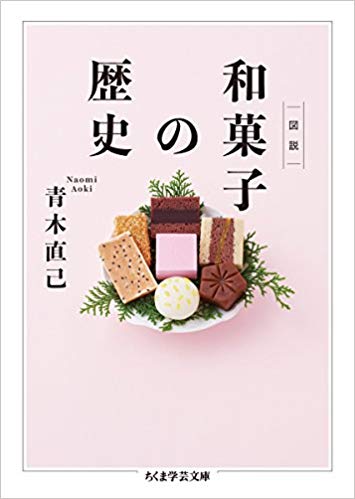2月9日。今日は大福の日
2月9日は株式会社日本アクセスが制定した大福の日。大福の2(ふ)9(く)の語呂合わせに由来する。
気取らない菓子として登場した大福
江戸時代は歴史上稀にみる安定した社会を実現した。そのなかでも元禄時代は、経済的な発展を背景として、華やかな元禄文化が花開いている。
さまざまに発展してきた菓子ではあるが、1600年代に入ってもまんじゅうや羊かんあるいは南蛮菓子などで、茶の湯の菓子といっても、ふの焼や昆布をはじめとする素朴なものであった。
しかし、元禄文化の王朝趣味の影響を受け、菓子に名前(菓銘)をつけ、デザインを工夫して、味覚・触覚・嗅覚のほかにデザインを目で見て楽しみ(視覚)、雅な菓銘を聞いて耳で菓子を楽しむ (聴覚)という、五感で菓子を楽 しむことが可能になった。
菓銘と意匠の工夫の例をあげれば、冬の朝、氷に閉じこめられた落葉を道明寺生地に小さく刻んだ柿の実を入れて表わした 「薄氷(うすらい)」という菓子や、古今和歌集にちなんだ菓子が工夫されるようになっている。
その結果、1693(元禄6)年に刊行された『男重宝記』には、約250の菓銘と24種の菓子意匠が記され、あるいは菓子絵図帳とよばれるものが菓子屋で作られた。元禄時代の京都において上菓子が完成し、その後は京菓子の名で全国に広まっている。
また、『古今名物御前菓子秘伝抄』などの菓子製法書が出版されることによって菓子の世界は広がりをみせ、一方、江戸を中心に気取らない大福餅・幾代餅あるいは米まんじゅうをはじめとする庶民の菓子が発展する。
その後、1800年前後には煉羊かんが創製され、文化・文政期 (1804~1830年)には和菓子の爛熟期を迎えている。
(日本食糧新聞社『食品産業事典 第九版』(引用箇所の著者:全国和菓子協会 藪 光生))