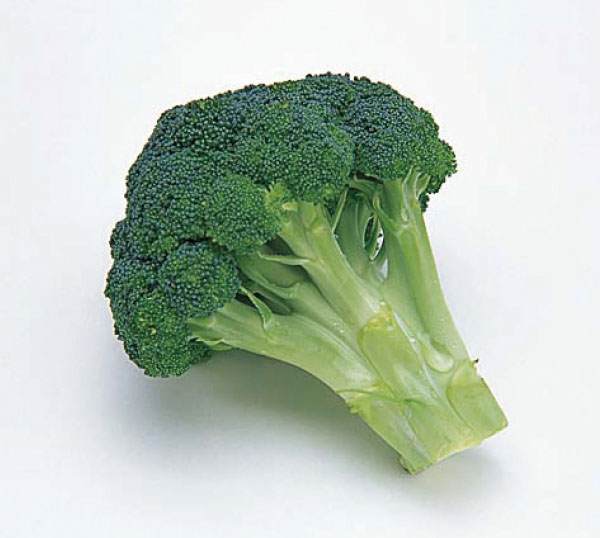百歳への招待「長寿の源」食材を追う=「よもぎ茶」健胃・神経痛などに
よもぎは山野に自生するキク科の多年草である。本州・四国・九州をはじめ東アジアの温~暖地域に広く分布する。平地から山地まで荒れ地や道路わき、畑のへりなど日当たりの良いところに生える。
別名でモチグサ・フツ・モグサ・ヤイトグザ・ヨゴミなどと呼ばれている。中国では艾葉(ガイヨウ=アイ・イエ)と呼び、重要な漢方薬剤となっている。
よもぎは春の摘み草の代表的なもので、若芽・若菜の良い香りが口中に広がり、また彩りも良く春を感じさせる。食品利用以外にも薬用効果は極めて高い。また品種も多く日本だけでも三〇種を超える。
茹でて細かく刻んだものをすり鉢でよくすりつぶす。これを餅につき込んだものが草餅で雛の節句には欠かせない。上新粉や白玉粉と合わせたものをつき混ぜて蒸すとよもぎ団子ができあがる。
よく水にさらしたものを、ゴマ和えやみそ和え、炒めものにしたり、汁の実や炊き込みご飯にも利用、葉を天ぷらにしても美味。
よもぎの成分をみると、タンパク質のほか、繊維・ビタミンA・B1・B2・C・カルシウム・鉄・リンなどが豊富で優れた栄養食品といえよう。祖先は良く知らずに栄養をとっていたのである。
よもぎ特有の香りのもとはチネオーレと呼ぶ精油で、これが健胃・腹痛・貧血・神経痛・リウマチ・心臓病や強壮などに効果大といわれている。ただ食品に混ぜて食べるのもいいが薬茶・薬酒利用、また入浴剤としての利用も。
よもぎの葉の採取は6~9月の間ならいつでもよく、よもぎ茶用であれば葉の生育の盛んな初夏から夏にかけてが香りも高く、適期といえよう。
茶葉を刈り、よく水洗い・水切りし、粗刻みしてから半日ぐらい天日で乾燥、陰干しして保存する。漢方薬店や健康食品店では艾葉、またはよもぎ茶の名前で販売されている。
よもぎ茶の場合、煎茶よりやや多めの乾燥葉をいれて一日数回保健茶として愛飲する。効用として消化促進・食欲増進をはじめ腹痛や下痢・便秘にもよい。
よもぎ酒も健胃・強壮に効果的。ホワイトリカー一・八リットルに乾燥葉一五〇グラム、氷糖二〇〇グラムを用意して漬け込み二~三ヶ月たてば飲み頃。一日二から三回、二〇〓程度を飲む。
よもぎ湯も、乾燥葉を風呂に入れるだけで身体が暖まり、湯冷めしない。肩こりや冷え性にもよく効く。
中国では葉・実ともに利用している。艾葉液の注射薬は慢性肝炎に用いて有効率九二%の好成績をみせている。その他、肺結核・喘息・慢性気管炎などに特効を上げている。その他血行を良くするので高血圧や神経痛にもいいと言われている。
艾葉はほとんど中国全土で採取され、手軽であり、価格も安く食材としても優れ、薬効面でも顕著、庶民性もあり人気度は抜群である。