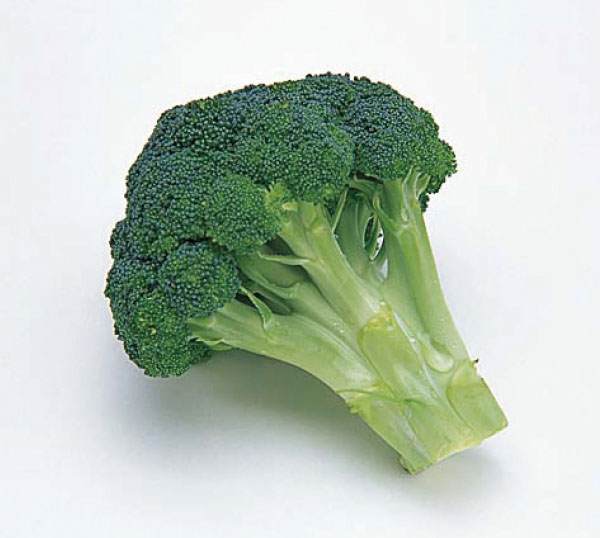知ってるようで知らない「砂糖の活用術」 カルシウムやウーロン配合物も
砂糖は調味料として甘味をつけるために不可欠な食品であり、塩味・酸味・苦味とも調和し、多様な味をつくり出す。
たとえば紅茶やコーヒーに入れると苦味が緩和され、夏みかんにかけて食べると酸味がやわらかくなる。
砂糖は種類によって甘さが違う。黒糖(黒砂糖)が最も甘みが強く感じ、三温糖、上白糖(白砂糖)、グラニュー糖、白ざら糖、氷砂糖の順でこれが軽くなる。
純度の高い砂糖の方が甘味は軽い。同じ白砂糖でも結晶の大きなものほど純度が高いので甘味は軽い。三温糖や黒糖がこくのある甘味を出すのは砂糖の主成分であるしょ糖以外の物質の混在が多いためである。
健康ブーム、自然食人気の中で、この三温糖、黒糖の売れ行きが良くなっているという。
一般に三温糖と呼ばれるのは精製三温糖で、上白糖、中白糖の精製の後にできるものだ。したがって多少ミネラル分の含有量は高いが、純度が低く、カラメル化して色がついているので、これは健康食品ととらえるよりも煮物などに使う調理用の砂糖と考えるのが良いだろう。
精製三温糖とは別に精糖メーカー各社は健康を考慮した砂糖を製造・販売している。
日新製糖(株)は中白糖に炭酸カルシウムを添加し、カルシウムをよく吸収する良質な牛乳たん白質成分CCP(カゼインカルシウムペプチド)を配合した「カルシウム糖」を出している。
大さじ一杯に約五〇ミリグラムのカルシウムを含む。普通の砂糖と同じように使いながらカルシウムを補うことができる。
三井製糖(株)は三温糖に牛乳から生まれた乳清カルシウムと歯垢を作りにくくするサンウーロン(烏龍茶から抽出した成分)を配分した「かしこいかあさんの三温糖」を製造・販売している。
ほかに三温糖タイプとしてステビア入りの東洋精糖(株)「ハーフシュガー」、昔ながらの方法でサトウキビからとれた粗糖を漉し、鉄釜で煮つめ攪はんしながら自然に乾燥させて作った宮崎製糖の「手づくりふるさ糖」「玉砂糖」(粗糖に糖蜜を加えたもの。ミネラル分を多く含み、その上カロリーは控えめで自然の風味やコクがある)がある。
また、台糖(株)はビタミンB1、B2を強化しカルシウムを加えた「ビタカルシュガー」を製造・販売している。
砂糖もでんぷんもグリコーゲンも、摂取されて腸内に入れば同じブドウ糖になって吸収される。
砂糖は吸収が早く、ブドウ糖の供給を迅速に行うことができる。緊急の場合には、糖が重要であり、われわれの身体が進化の過程でそれに適応するようにつくられてきたことを示す。
肥満、糖尿病、虫歯の観点から砂糖の功罪を論じると、砂糖の過剰摂取は健康上よくないのは事実だが、一部には砂糖の害を強調するあまりの、科学的な裏付けのない俗説が根強く残っている。虫歯に関しては要因の一つではあるが、歯の衛生を保つことによって防止することができる。
また、砂糖の白色は漂白したものではなく結晶の透明度による光の反射によるものである。
砂糖の第一の魅力は美味しさだ。健康ブームの中にあって砂糖のマイナスイメージが作られているが、初めて日本にもたらされた頃は薬として用いられていたという。砂糖は上手に使うことが特に重要な食品なのである。