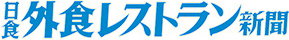シェフと60分:三笠会館/フレンチレストラン「榛名」山田豊年料理長
「給料をもらうと、すぐ本代に消えるぐらい専門書を買っていました。二子多摩川の寮と店を往復する電車の中で、料理用語の辞典を真っ黒になるくらい読み込んだものです」
料理人となってから、コツコツと地道に努力を積み上げてきた。その軌跡がそのまま、老舗の伝統と味を守り続けてきた三笠会館の歴史と重なっている。
「毎週金曜日のローストビーフの日にホールに出ると、四〇年前にお父さんに連れられて来たという人がいる。子供の時、両親と来て良かったから、自分も子供を連れてきたと言ってくださる。そういうお客さんも大切だし、若いお客さんに対して、新しい料理もないといけない。また、ローストビーフやインドカレー、ビーフシチューなどの親しまれてきた伝統の味を、若い人に伝えていくのも大事な仕事なんです」
いまはもうメニューから消えた、まぼろしの唐揚げの注文にも、当時のレシピを再現してこたえることがあるという。
本店ののれんを背負って、オーナーシェフのように好きなようにやるわけにはいかない。
その一方フランスに行き、新しい素材やハーブの使い方を先取りする。伝統料理に工夫を加え、いっそう良い物を作ろうと意欲を燃やす。
「ローストビーフはもっと改良してもいいと思ってます。たとえばフランスでは肉に切れ目を入れニンニクを丸ごと挟んで焼く。伝統を守りながら挑戦もしていかないと前に進まない」
三年前の研修では、フランスで三ヵ月間住み込みながら働いた。そこで学んだ新しい素材や調理法を、メニューに取り込めないかと考えた。
「技術的には、素材も調理器具もほとんど日本とは変わらないですね。メニューはオーソドックスで、プロバンスなどでは田舎の素朴な料理をちゃんと守っている」
だが、日本にない食材もある。パンのレシピを持ち帰ったが、小麦粉は税関で止められてしまった。
「ブルターニュの塩の牧草を食べている子羊は、身がかすかにハーブの香りがする。そういうおいしい物を提供したい。二〇年前にはなかった生のハーブがいまは普及したのだから、塩の子羊が手に入る可能性はあるかもしれない」
素材に対しては、人一倍敏感だ。実家は農家で、酪農と果樹、野菜、コメとなんでもやっていた。季節感と品物の良しあしが子供のころから身体に染みついている。
「東京出身の人は旬を知らない。私はいい所に生まれました」
一番こだわったのは、玉ネギ。オニオングラタンスープの材料で、一番高くて質の良いのが淡路島産。甘くて実が厚い。実家もその玉ネギを作っていた。
「仕入れる材料を見る目がないと、うまい味がでない。同じようにソテーしても味が違う。春にはタイを、明石と鳴門の知り合いの漁師から宅急便で取り寄せている。渦潮にもまれた魚と築地で買った魚の違いは、ポワレで火入れしたときに分かる」
目利きには自信を持っている。業者が毎朝、持ってくる食材は必ずチェックし、悪いものは持ち帰らせる。
近年、イタリアンが隆盛を極めているのに対し、フレンチは元気がない。ホテルのレストランも次々と撤退していく。
「日本のフランス料理は、いきなり高い所に置かれ、そのままになっている‐‐」と、時代の変化に対応しきれないフレンチの現状を憂慮している。
そのため、フランスでは、「一般家庭のフランス料理とはどういうものか」を見たかった。実際、家庭に招かれてみると、最初にサラダ、前菜、それからすぐメーンのラムのもも肉の煮込み、あとはチーズとパンと簡単なデザート。
「別のところではクスクスが出たけど、それがごちそうだという。つまりそういうものを食べている。日本でいうブイヤーベースなどは全然出てこない」
日本でフレンチというと、一万円も二万円もするコースを、誕生日などのハレの日に食べるというように出来上がっている。
「誕生日などに来る人はいても、ほかの人は来ない。その人たちが来やすいような価格と料理をもっと広げて、こんなにおいしいなら、もっと良いところにも行ってみようと思ってもらえれば、高級レストランにも来るようになるのではないか」
最近は、日本でもビストロといって家庭料理を出すところが出てきた。「一度家庭料理から浸透し直せば、また盛り返してくる」という思いを強くしている。
自身も「フランスは、パリより地方に得るものがある」と、地方の伝統料理を吸収して、本店のメニューに新しい風を吹き込む。
◆プロフィル
昭和24年3月1日淡路島生まれ。高校卒業後、上京。アルバイトで厨房に入ったのをきっかけに料理人の道に入る。
二〇歳の時に、知り合いを通じて三笠会館の東銀座店に入店した。調理場で、調理学校出身の同期や後輩に、「負けたくない。この人たちを追い抜くためにはどうしたらいいか」と、持ち前の負けん気から猛勉強をしたという。
また、「宴会でだれにも負けないものを作ってやる」と始めたのが、氷細工。休日のほとんどを、帝国ホテルの横にあった教室に通って過ごした。十何年続けて、北海道・旭川の氷祭りに作品を出品したという実力の持ち主だ。
平成3年、本館「榛名」の料理長に就任。
渡仏は三回。プロバンスやブルターニュといった地方の魅力に、新たなフランス料理の方向性を見い出している。
文 加藤さちこ
カメラ 岡安 秀一