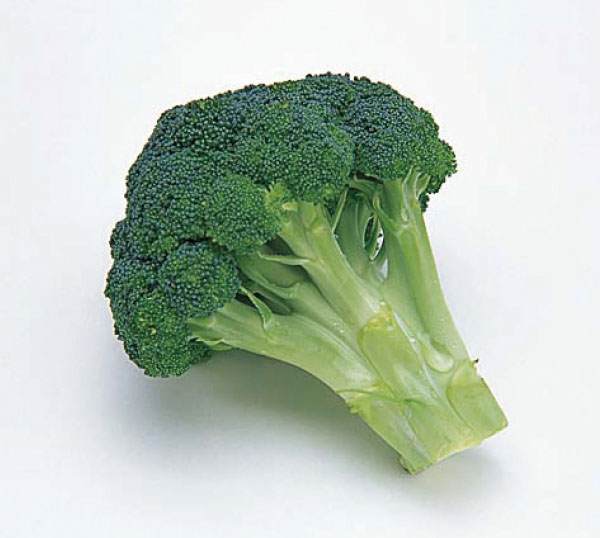本の中から:早起きと朝新習慣のすすめ 朝を制するものは人生を楽しくする
秋の夜長でついつい夜更かし、日の出の時間も日に日に遅くなり、布団の温かさも離れがたく……。そんな今日この頃に「喝っ!」を入れてくれる本を2冊ご紹介したい。
『週イチの早起きで、「朝型人間」の誕生!!』(三五館)はズバリ、午前5時に起床することを勧めている。これから向かう冬至ともなると日の出は6時50分頃、まだ外は真っ暗な時間にどうして起きなくてはいけないのか。それは、自律神経の中で活動を活発にさせる交感神経と休息させる副交感神経は、前者は昼、後者は夜に働きが強くなるが、その切り替えの時間帯がちょうど午前5時に当たるからだそうだ。
「この時、身体はとても不安定な状態におかれている。何にでもいえることだが、同じ状態を維持している時よりも変化する時の方がストレスは大きい。だから、不安定な時間帯はなるべく静かにして……というのではなく、むしろ一気に飛び起きて身体を動かしてやる」。
著者・税所弘氏は、『早起き心身医学研究所』の所長で、前著でも「人間の脈拍が一番多い時間は午前5時頃といわれている。なぜ5時頃なのかというと、気温・湿度・空気イオンの状態が一番悪い時だからなのである」と展開している。うつ病患者や神経症患者は特に、目覚めてから寝床から離れられず、あれこれと考えすぎてしまう傾向があり、これを直すにも「飛び起き」が有効という。
とはいっても「それでは明日からさあ!」と、急に早起きになれるものではない。研究所では三カ月かけて徐々に早起きになれるよう指導しており、そのための助走として「週一回だけ」という方法が登場する。
「秋だからため息が出るなぁ」なんて人、もしかして寝坊癖が問題だったのかも。試してみる価値はありそうだ。
『「朝の習慣」を変えると人生はうまくいく!』(青春出版社)は、『自分を変える魔法の口ぐせ』などの意識変革本で評価の高い医学博士・佐藤富雄氏が、一日のモードを決める「朝」という時間帯に焦点を当てて、“成功哲学”ではなく“成功科学”を展開している。要する時間はたった三分で、その間にできる効果的な「脳の使い方」「体の作り方」「心のきたえ方」が描かれている。ここでは「脳の使い方」の一部について紹介したい。
人間の脳は、人間の意志を受けつけずに生体コントロールを行っている自律神経系担当の古い脳と、ものを考えたり判断する意志の部分担当の新しい脳の二つで構成されている。古い脳は、過去・現在・未来の区別、言葉における自他の人称が分からない。だから「人の悪口を言ったり、失敗を望んだり、呪ったりしていると、それを口にした本人がダメージを受けてしまう」、また年中「不安だ、心配だ」と口ぐせのように言っていると、「自律神経系が困ったことになっているのだな、と理解して、実際に困った状況をつくり出してしまう」のだそうだ。「過去の失敗、苦労話、愚痴も絶対に禁物」だ。なるほどストレスが身体に悪いわけだ。
そこで朝、この脳のメカニズムを味方につける。三分間、「自分の“成功シーン”を思い描いてみてください。頭で想像するだけでなく、具体的な言葉で表現していくと、より多くの情報を、より確実にインプットできます」。
○ベッドを出たらベランダに出て「今日もいい日になるぞ」と第一声を発する
○鏡の中の自分に向かって明るくあいさつ、にっこり笑いかける
○今日という日をどんな一日にしたいのか、メモに書き記し未来の自分へのメッセージとする
‐‐など具体的方法も満載だ。