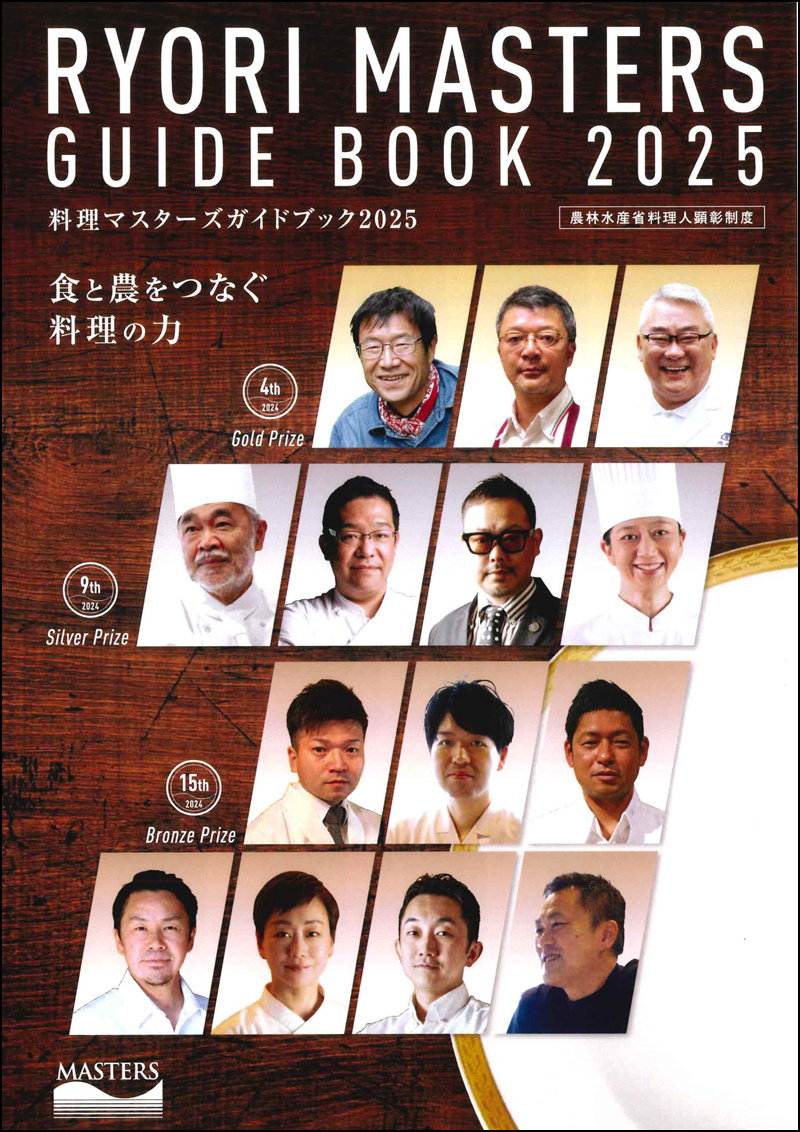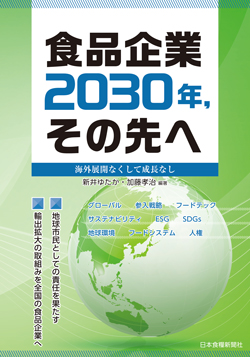代替肉、食品革命をリードできるか 日本でも相次ぎ登場
世界的なSDGs(持続可能な開発目標)理念に賛同する食品企業を中心にプラントベースフードの開発が活発化し、2020年は日本において“食品革命”の幕開けになり得る。それをリードする代表格となりそうなのが、代替肉(フェイクミート・ベジミート)だ。ビーガンやベジタリアンといった“食”に関する主義は、思想や宗教上のタブー、あるいは地球環境保全、天然資源消費の抑制、動物愛護など、多面的な理由が背景となっている。菜食主義は欧米に多いが、アジアでもインドや台湾などでは信仰的な理由からかなり自然な形で食習慣として根付いている。一方、日本社会ではまだ浸透していないのが現状。だが高まる健康志向の中で、ヘルシーな食事としての代替肉の認知度は徐々に広がりつつある。(武藤麻実子)
巨大マーケットを持つ現在の米国では、代替肉の加工食品の開発に余念がない。マクドナルドやデニーズとも契約を結ぶビヨンド・ミート、「Impossible Burger」を完成させたインポッシブル・フーズ、米国ネスレが買収したスウィートアースなどが市場をリード。
そして、これら企業はアジア市場にも目を向けている。「Impossible Burger」は香港でも提供し、台湾のモスバーガーはビヨンド・ミートのソイパティを使ったハンバーガー「MOS Burger with Beyond Meat」を発売。しかし、いずれも現時点で日本進出や素材の輸出といった話は聞かない。ビヨンド・ミートに出資していた三井物産の発表で、日本でのビヨンド・ミート製品販売計画の取りやめも今年8月に明らかになった。理由はさまざま推測されるが、世界から一歩出遅れた感も否めない日本市場で、代替肉がどのようにブレークしていくかは、やはり味づくりの完成度とイメージ戦略による部分が大きい。
先述の通り、日本人の場合はヘルシー志向による選択が多い。また残念ながら「どうせおいしくない」といった思い込みが一般的に払拭(ふっしょく)し切れておらず、このマイナスイメージを打ち砕くほどの“おいしさ”が必須となる。ただし、おいしさと一言でいっても、食感・香り・見た目を含む複雑な要素が絡み合うため、製造技術がこの“食品革命”を左右する大きな鍵の一つとなる。さらに購入しやすい価格帯、幅広い選択肢といった点もクリアすべき課題だ。
日本の市販品で代替肉を採用した新製品は、ハンバーグやソーセージの展開をする「ゼロミート」シリーズ(大塚食品)、レトルトパスタソース「大豆のお肉のボロネーゼ」(マルコメ)、大豆肉の具以外も動物性食材不使用とした「ニュータッチ ヴィーガンヌードル〈担担麺〉」(ヤマダイ)、独自のチーズ代替品と大豆肉をトッピングした「家庭用ヴィーガンピザ〈新大陸の勇者〉」(マリンフード)など、調理済み、あるいはすぐに食べられる簡便さが特徴的。さらにパッケージでいかに“本物の肉”に近づけたかを強調する商品がある半面、代替肉を大きくうたわないものもある。あるいは“大豆”でヘルシー感を訴求する商品もあり、一概に“代替肉”そのものを強調しているわけではないことも見えてきた。
日本の消費者に向けては、肉の代わりという意識から離れ、植物由来というポイントやそのさまざまな背景価値に重きを置き、日々の生活に自然に取り入れる導引が必要と考えられる。
◆解説:10年後には15兆円規模も
海外のアナリストや金融機関の予想によると、世界の代替肉市場は10年後に15兆円規模、食肉市場のシェア1割程度へ拡大するとみられている。
国連で採択されたSDGsの広がりを受け、飢餓の撲滅や海洋・陸上資源保全といった17項目の目標に取り組む機運が世界的に高まっていることから、こうした動きが代替肉の開発や需要拡大の追い風になってきそうだ。
日本でも来年の東京五輪大会の開催へ向け、かねて一部の食品メーカーがインバウンド需要対応などで代替肉の商品化に着手してきた。長期的な健康志向も背景に、国内で今後どのような市場が形成されていくのか。関連企業の取組みに注目が集まる局面だ。(篠田博一)