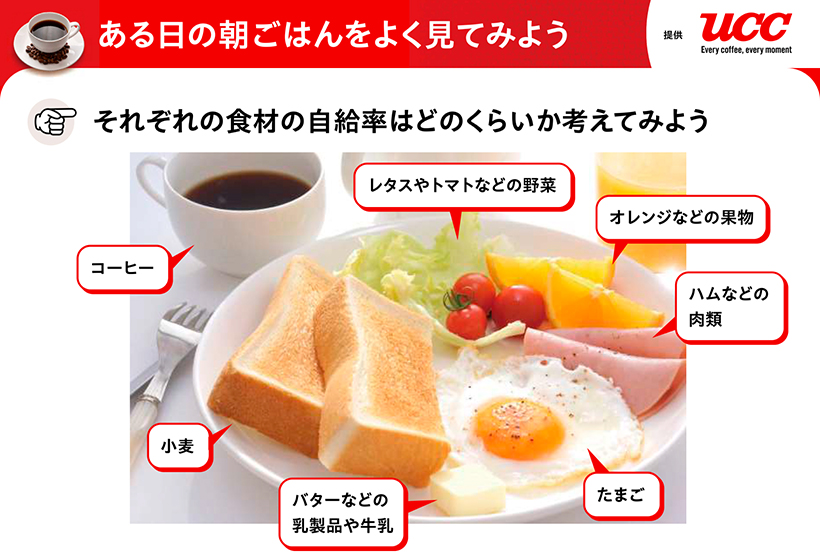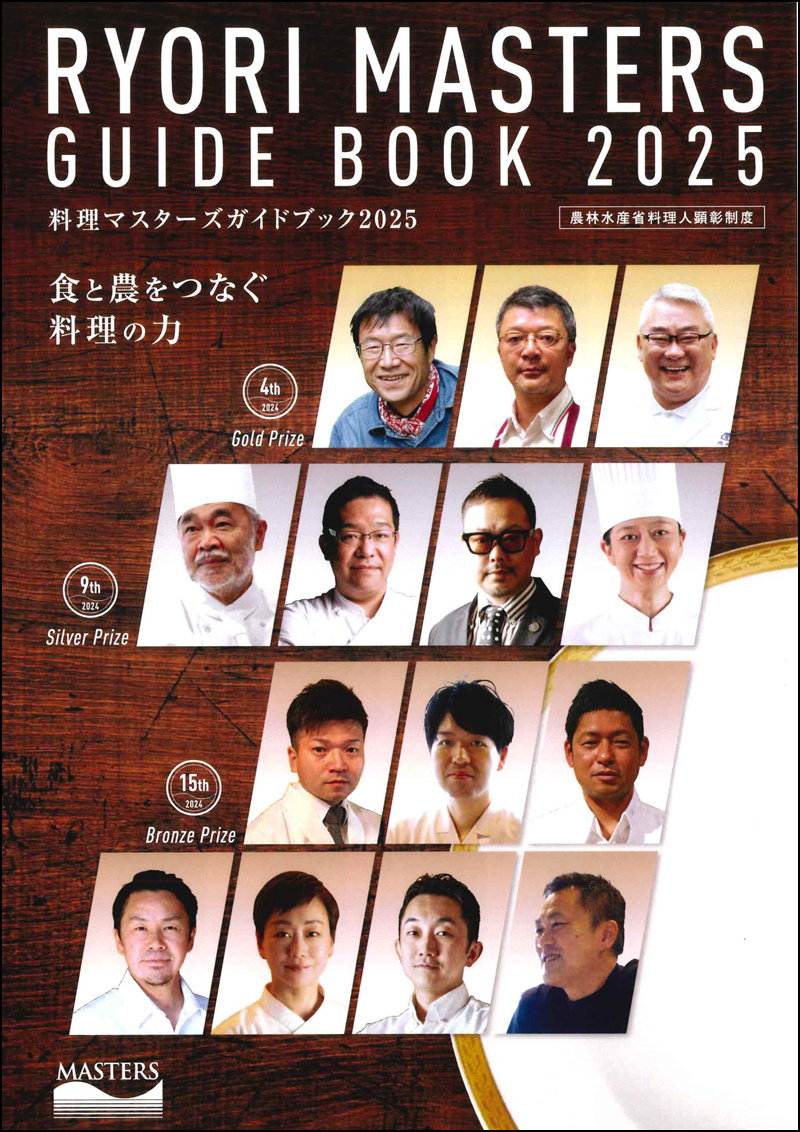肉選びのマルチスタンダード化が消費者の舌をいやし続けることにつながる
東京オリンピックを迎えようとしている日本に対して「アニマルウェルフェアを順守した食肉飼育が十分ではない」という理由から、西洋諸国の業界関係者から批判の声もある。世界規模で食肉業界を俯瞰(ふかん)すれば、人口増加問題やエシカル志向の中で培養肉やアニマルウェルフェアについて考えなければならない。60年前よりアニマルウェルフェアの視点で肉牛飼育を行う「なかやま牧場」の関東エリア営業所長および株式会社Meattech代表の中山智博氏に取材し、今後の食肉業界について考えた。
生産者および消費者の食卓を救うために、食肉評価の多様化が求められる
アニマルウェルフェアとは、家畜を動物としてとらえ、誕生から死ぬまでの期間、可能な限りストレスや恐怖を与えずに健康的な飼育を目指すことだ。「動物福祉」ともいわれている。
日本や中国、シンガポールなどのアジア諸国では、霜降り肉が好まれA5ランクの肉が評価される。よく聞くこのA5やA4ランクという等級は、「肉の霜降り度合い」や「色沢」(色と光沢)を基準としており、肉の「うまみ」を表す指標ではない。
もちろん赤身がちな肉への需要もあるだろう。しかし現在の評価基準では霜降り肉が高値で取引されるため、A5ランクの肉作りを目指す食肉業者が多い。
一方で中山氏によると、西洋諸国の消費者は等級の他にJGAP認証を重視しているという。JGAPでは「農場のアニマルウェルフェア」「労働安全や人権福祉」「環境保全」などを保証する。しかし、日本ではJGAPのような認証で肉を選ぶ消費者は少ないため、食肉業界もアニマルウェルフェアではなく等級を意識した飼育となるそうだ。

どちらが正解という話ではないが、評価の多様化は食肉産業の活性化につながるだろう。その例として、中山氏はオーストラリアの食肉業の実態を教えてくれた。
「アジア向けに霜降りの牛を作る農園と、欧州向けにアニマルウェルフェアを順守して育てられた赤身がちな肉を作る農園とで分かれており、それぞれが別の市場で成功している」
昨今、本当に良い日本酒が海外流出していると言われるように、等級至上主義でなく健康的においしく育てられた和牛が、日本人がその真価に気付く前に高値で海外流出し始める可能性がある。等級にとらわれず、こだわりを持って作られたおいしい肉を評価できる新たな指標を持たなければ、肉の生産者は減り、消費者の食卓幸福度が下がる未来が待っている。

アニマルウェルフェアな食肉ブランドが日本でなかなか育たない理由は
まず、消費者の意識がアニマルウェルフェアに向いていない。加えて飲食店もその路線で「売り」をつくる戦略をとる所はほとんどない。しかし、これはオリンピックで多くの西洋諸国の方が訪日することを考えると、ビジネスチャンスの喪失ではないだろうか。
オランダにはレストランをアニマルウェルフェア視点から評価するレストランレビューサービスまであるそうだが、日本でもこのようなサービスが生まれる未来はあるのだろうか。
また生産者側から、アニマルウェルフェアを軸にブランド肉を作っていきたいと思っても、なかなか難しいことがあるそうだ。
「日本の食肉加工の工程では、生産者である農場と販売業者が完全に分かれており、一度生産者の手元を離れた肉は生産者も知らぬ所で流通網に乗る。こうした事情から、直接生産者が消費者にメッセージを伝えたり、ブランディングを行うことが難しい」と中山氏は生産者サイドの課題を語った。
中山氏は、自社のアニマルウェルフェアで育てられた肉をブランディングすることも考えたことがあるが、「D2C(Direct to Consumer)のような形態で生産〜ブランディング〜販売までを一括で行うことが、食肉業界では難しい」と語った。
アニマルウェルフェアが必ずしも善というわけではなく、思想の問題もあるだろう。しかしポリシーを持った生産者が評価を受け、経済的恩恵を預かりやすいもう一つのスタンダートが生まれること自体は望ましい。

培養肉がリアルになるのも近い未来?
ATカーニー社が予測する食肉業界の未来では、2040年には食肉の60%以上が培養肉や人工肉になると言われている。培養肉は「リアルでない劣った肉」なのだろうか?
中山氏の話を聞くと、リアルミートにはない付加価値を培養肉に感じることができた。例えば、ラボで作られる肉は無菌状態であるため、生食というグルメを可能にしたり、免疫力の下がっている時に恐る恐る肉を食べる必要もなくなる。培養肉の「うまみの方程式」が見つかり、大量に生産することができれば、高級肉の味を誰でも楽しむことも可能になる。
現在、中山氏はなかやま牧場と食肉業界の未来のために、株式会社Meattechを立ち上げ培養肉やゲノム研究を日本の大学機関などと行っている。
培養肉の研究は、現在世界中で投資が集まり開拓される分野である。プレイヤーは既存の食肉業界の人から、化学メーカーまで。今後、培養肉を扱うベンチャー企業などはますます増えることだろう。
日本では輸入飼料高騰による食肉産業の疲弊を防ぐため、「飼料米」生産に補助金をつけるなどして国内飼料供給を支援する。しかし飼料米はトウモロコシの飼料と異なって生で提供すると消化しづらいため、火を入れる必要がありその手間のために導入しない農場も多い。
20年後のわれわれは、リアルミートとアーティフィシャルミートを気分や経済状況によって使い分ける器用な人類なのかもしれない。(フードプロデューサー 古谷知華)