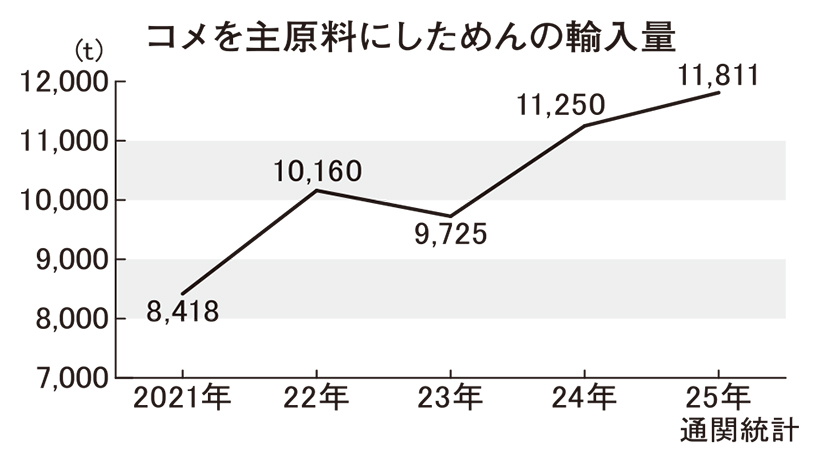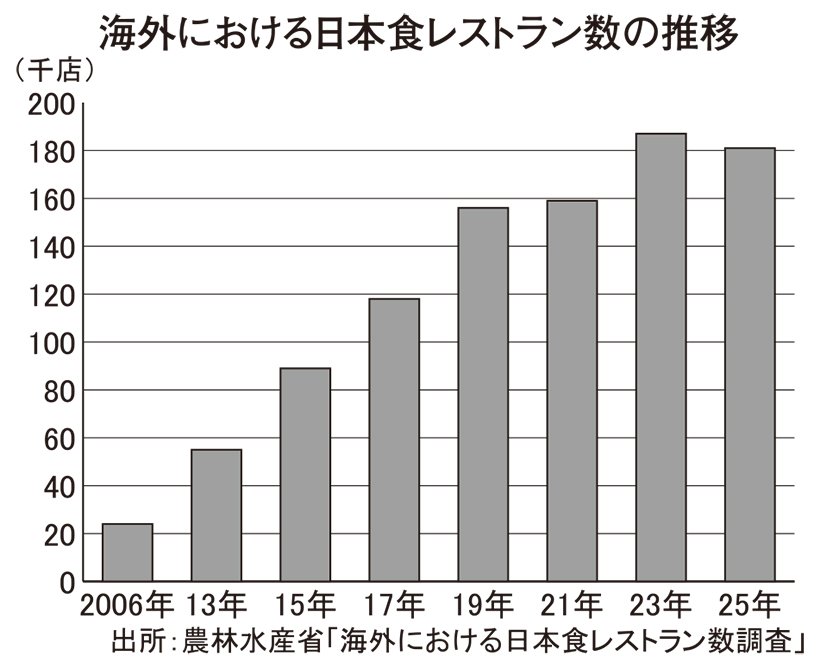紐1本でインスタ映え ブランディングのプロが仕掛けるフルーツ大福の行列店
名古屋の覚王山のフルーツ大福店「弁才天」は、2019年秋の開店からすぐに評判が高まり連日列ができる店へとなっていった。評判の高さの理由は、フルーツ大福そのものの質の高さはもちろんのこと、その価値を広めるためにブランディングやマーケティングなどの工夫が施されている点にある。
広告会社から独立、和菓子の世界へ
名古屋地下鉄東山線覚王山駅。駅から閑静な住宅街に入り10分ほど歩いた先、大きな道路に面した角に弁才天はある。昔ながらの和菓子屋さんの風情が感じられる外観は、ずっとそこに存在したようにしっくりと馴染む。
平日だというのに人が途切れることはない。控えめな広さの店内に入れば、商品であるフルーツ大福のディスプレイが目に飛び込んでくる。大福をカットし果実の断面が見える形でサンプルが並んでおり、果実が鮮やかな色彩で心が躍る。

弁才天オーナーの大野淳平氏は、もともと広告会社に勤務していたが独立。小売・サービス業界をメーンクライアントとし、デザインや広告、PRなどの面からコンサルティング業を行っている人物だ。多くの企業と仕事をしていくなか「自分のプロダクトを起こしたい」そんな心情が高まったことで完成した事業の1つが弁才天だった。
飲食業界のクライアントも多い大野氏は常々思うものがあった。非常に高い技術を持ち、昔からの伝統を引き継いできた素晴らしい和菓子があるにも関わらず、表現するための組み合わせが間違っているせいで、価値をしっかりと伝達できていないのではないか。
マーケティングとは「どこで、誰に対し、何をするか」が大きな3つの柱になると考える大野氏。その組み合わせが適した場所にはまっていないもどかしさを感じることもあったという。弁才天にはそんな思いを抱く大野氏がこれまで培ったノウハウが存分に注ぎ込まれている。
細部までこだわり抜かれたフルーツ大福
弁才天のフルーツ大福のこだわりは細部にわたる。求肥は100%羽二重粉使用だ。羽二重粉とは、餅粉の中でももっとも粒子が細かく高級和菓子に使われるもの。驚くほどによく伸び、食感は非常に滑らか。商品は全て毎朝手作業で包まれている。
機械で包むと量産は可能になるが、求肥が分厚くなり、乳化剤が必要となる場合がある。余分なものをできる限り排除した引き算の美学があった。控えめな甘さで果実の味わいを邪魔しない、確かな存在感がある。

紅ほっぺやピオーネ、温州みかんなど色とりどりの果実は、毎朝北部市場で購入している。仲買人からその日の良いものを目利きしてもらい購入しているのだ。大福に合わせた果実の酸味、甘味のバランスは絶妙だ。求肥と果実がお互いを引き立て相乗効果が生まれている。
パッケージである紙袋や箱のデザインも秀逸だ。高級感のあるしっとりとした和のデザインは、店舗の外観やパッケージによくマッチしている。

覚王山は住みたい街としても名前が挙がることが多く人気がある。高級スーパーやレストラン、老舗の菓子屋が点在し、落ち着いた住宅地が広がる街だ。弁才天はそんな立地や客層などすべてを包括したブランディングがきれいにはまっている。
「誰かに見せたい」感情を行動につなぐ餅切り紐
フルーツ大福が入っている箱を開いたとき、見逃せないものがある。付属の「餅切り紐」である。弁才天で購入すると大福を切るための紐(ひも)が付属している。
大福などの米粉を使ったやわらかい和菓子は包丁で切り分けようとしても上手に分けられない。伸びる生地が包丁の壁面に付着し引きずられてしまうのだ。そこで使われるものが細い紐である。紐で大福を結ぶようにして交差し引くことで、断面を美しく保ったまま切り分けることができるのだ。
このこと自体は昔から利用されている方法であり、ご存知の方も多いだろう。同封しているリーフレットにカットの仕方が記入されているものもある。しかしいざ開封したとき即座に食品をカットする紐を用意することは難しいのではないだろうか。

購入の際店頭で見た大福の美しい断面が並んだディスプレイ。それを再現しようと思っても包丁で失敗してしまっては台無しだ。その心情を反映させたのだ。餅切り紐を付属させるアイデアは大野氏のものだ。
「素材そのものの味を丸ごと楽しんでほしい」という思いから、大福の中に含まれる果実は一つ一つが大きい。そのため大福も大振りだ。例えば購入後、家族や友人、パートナーなど、誰かとシェアしたいと思ったとき、餅切り紐があるだけで、スムーズに行うことができる。「大切な人とシェアをしてより多くの種類を食べてほしい」そんな大野氏の気持ちも込められている。
「#萌え断」のハッシュタグが拡散を後押し
また、インスタグラムで「弁才天」を検索すると美しい大福が並んでいるのがわかる。ハッシュタグ「#萌え断」なども併記され、拡散を後押ししている状態だ。大野氏はこれらインスタグラムなどSNSでのマーケティングも視野に入れて餅切り紐を同封した。
ツイッターやフェイスブック、そしてインスタグラム。複数のSNSが日常的に使われるようになった今の時代。どの場でどんなマーケティングを仕掛けるべきなのかは、商品の立ち位置とSNSの性質を理解することが必要である。
「#萌え断」はカットした際に表れる色鮮やかな食材の断面に付けられる。フルーツサンドイッチなどによく見られるハッシュタグである。他にも「#かわいい」や「#インスタ映え」「#ファインダー越しの私の世界」など、文字情報ではなく画像を求めるハッシュタグがあふれている。

弁才天の美しいフルーツ大福はインスタグラムと相性が良いものだ。インスタグラムはビジュアルコミュニケーションがメインのSNSである。リツイートなどがないインスタグラムはハッシュタグによって人々の目に触れていく。拡散力は低いものの、共感性が高く個々の心に深く浸透していきやすいのだ。
美的感性を刺激するインスタグラムは「フルーツ大福の美しい断面を投稿したい」という気持ちの行き場に最適だ。手包みで作られるフルーツ大福は当然ながら同じものは存在しない。
紐でカットをするという、普段あまりない体験から達成感も感じさせ、表れた断面に感動し誰かに見せたいという気持ちを起こさせる。餅切り紐はその気持ちを後押しする存在となっているのだ。
餅切り紐も機械ではなく、人の手でねじり作られている。付属しているサイズの紐を機械で作ることは難しいのだと大野氏は言う。非常に骨の折れる作業ではあるが、餅切り紐は多くの意味を持つ大きな存在で欠かせない。
「和菓子の存在感を高めていきたい」
立地の選定、パッケージの考慮、餅切り紐などの工夫。すべて必要なことではあるが、やはり最も必要なものは、商品の質である。コンセプトに沿ったブランディングは非認知層へわかりやすく認知させることにとても有用ではあるが、それだけでは長続きはしない。人々の日常に組み込みリピーターとなってもらうためには、商品の純粋な品質の高さが必須といえる。
良いものを作ったとしても認知してもらわねば意味がなく、SNSをはじめあらゆるマーケティングは必須だ。だが流行とは違う、品質の高さという誠実なアプローチがあってこそ、さまざまな工夫が生きて、商品は残っていくのだ。

和菓子の技術や良い素材を詰め込んだ「弁才天」のフルーツ大福は、食べた人の心に深く長く残っていくだろう。
和菓子は多くの人に愛されているものではあるが、デパ地下の菓子売場をのぞくとやはり洋菓子コーナーの方が人は多い。そんな現状のなか「和菓子の存在感を高めていきたい」と大野氏は言う。
「海外のものを享受していくことも良いことです。しかし、自分たちが持っている日本本来の良さにも目を向けて、古き良きものを受け継ぎながら、新しくしていき、次の文化を作り上げていかないといけない」
和菓子の質や技術は非常に高いものだ。しかしマーケティングの失敗で消えかねないものも存在する。「一人でできることは多くない。同じ思いを共有する仲間と一緒に仕事をしたい」大野氏はそう語ってくれた。(栄養士ライター 瀬山野まり)
画像提供・取材協力:大野淳平氏(Shepherd Inc./CEO&Founder)
<覚王山 フルーツ大福「弁才天」>
愛知県名古屋市千種区日進通5丁目2–4
開店 : 午前10時〜午後7時 (完売次第閉店)