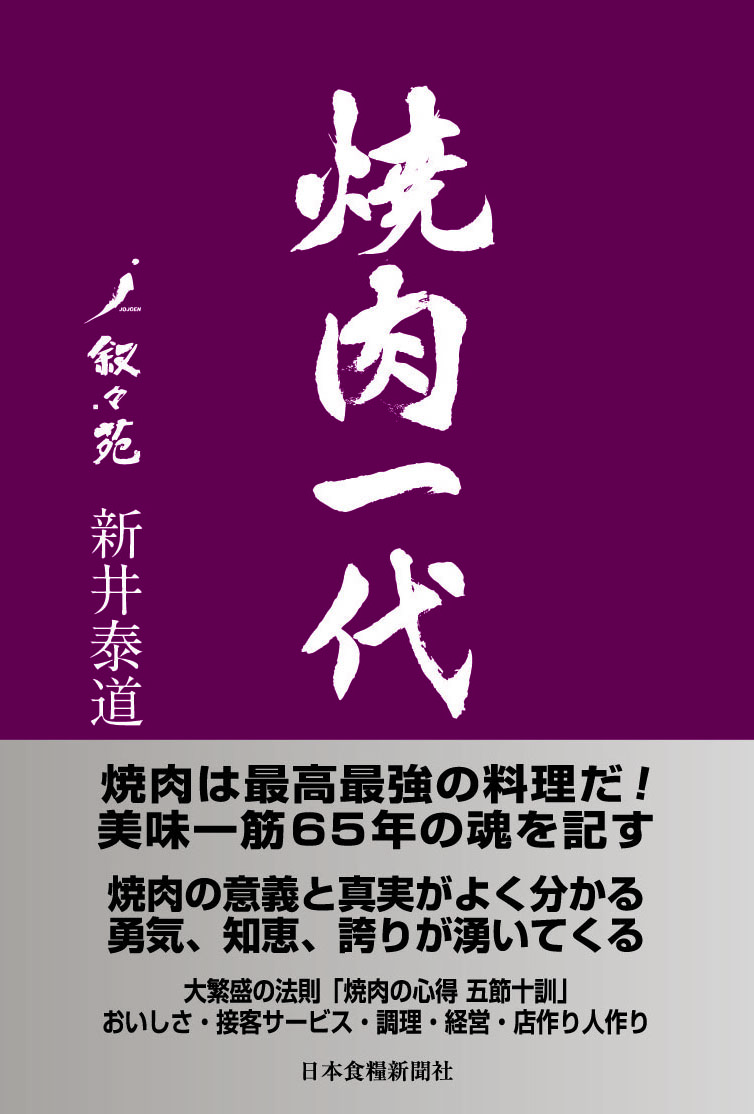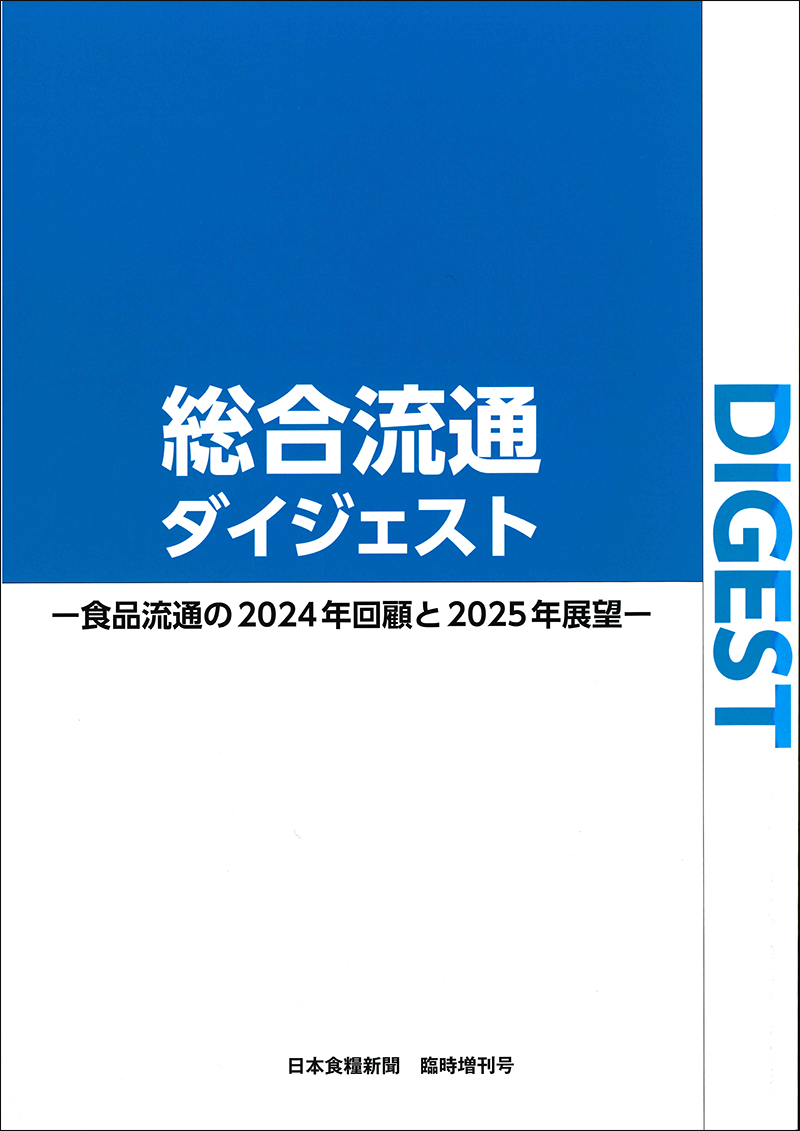チョコは自分へのご褒美…コロナ禍で消費が変化
バレンタインイベントができるのは幸せな環境なのだと感じたバレンタインだった。コロナの影響で今年は例年と異なる、といわれた。しかし今年といわず、毎年バレンタインの傾向は変わり続けていると筆者は感じる。その年の日本の世相を映し出すといってもよいだろう。そのため、2月14日が過ぎてもバレンタインの傾向や流れは、すべてのビジネスのマーケティングのヒントになると思っている。今回は、特に男女の関係性や人間関係に絞って振り返ってみる。
日本の世相を映すバレンタイン商戦にビジネスのヒントが
海外では男性から女性に花束を贈ることもあるバレンタインデー。日本の商戦化は、年に一度「女性から男性に告白してよい日」として、一大ブームになったのが最初だろう。その告白の“お供”としてチョコレートが選ばれた。いつから始まったのかは諸説あって定かではないとされる。

1985年8月12日付の日経産業新聞の記事には「元祖争いが激しくて起源はよくわからない」(日本チョコレート・ココア協会会長 中川赳明治製菓社長)と記されているとのこと。しかしこの記事が出た1985年には、すでにイベントとして確立されていたと、筆者は記憶している。
女性から男性へ告白することは、ある意味恥ずかしい。「女性は受け身であるべき」。当時はこういった考え方が根底にあってこそ、男性も女性もドキドキする特別な日となっていく。
「義理チョコ」「友チョコ」にみる関係性の変化
その流れが数年続き当たり前のことのようになるころには、「別に告白したい時にいつでもすればよいのでは」となり、わざわざ年に一度の日を待つ必要性がなくなると、告白の日は陳腐な日に変貌していく。そこで、次の一手に「義理チョコ」を生み出す。
義理チョコによってチョコレートは一層売れた。いくつチョコをもらったのか、という「数の勝負」の考えが背景にあったからである。たとえ義理でももらわないよりうれしい、という男性の見栄を満足させた。
また、バレンタインの義理チョコは、相手との関係性を保全する役割を担ってくれたことから、女性にも利便性のある慣習となっていく。「義理」という強烈な言葉を人へのプレゼントに使うこと。これも時代が変わった証明といえるのではないか。

義理チョコの役割は並行してお歳暮、お中元の代わりにする「お礼チョコ」にも広がっていった。そうだ、お礼チョコによって、もはや恋愛の感情は抜けていったのだ。そして、「友チョコ」だ。「男(彼氏)より、女(友だち)が大事」。頼りになるのは、女なのだ、という概念が生まれ、もはやバレンタインでは男性の存在が薄れてしまったのである。
女性から男性にプレゼントしたころは、人に知られずあげるものだった。しかし友チョコ時代になると、女性から男性への告白を公開する世界へとガラッと変わったのだ。「ぬけがけ」は許せない世界になった。女同士の集団意識に変わったのだと筆者は思う。
「自分チョコ」にみるお金と時間の使い方
その後は、「自分チョコ」だ。人から人へのプレゼントだったものが、自己完結になった。もう、面倒な対人関係は無用なのだ。自分で自分をほめて癒す「ご褒美チョコ」は、告白するイベントだった時代のものとは、まったく違う特別感になった。さらにその後、男性自身が自分に買う「オレチョコ」も生まれた。男女ともに「対自分」になっていったのだ。
筆者は少々寂しさを覚えるものの、ある意味では、一貫して「誰かを喜ばすためのイベント」であることには変わりない、といえるかもしれない。

2021年にはバレンタインイベントも開催されていたが、ネット通販で購入する割合が増加。また、巣ごもり需要の影響により家族で手作りするチョコも売上げが好調だった。一人暮らしの人は、「自分のために」。家族がいれば「家族で共有」。各々の生活スタイルの中で、自由にチョコを選ぶ。
コロナの要因は否めないが、こうした消費の背景はそれだけではないだろうと考えている。普段の生活の延長として、チョコで充実した一時を過ごす。自由でよい。決まりごとはない。かつてのドキドキはいらないが、楽しみは欲しい。自己中心的な選択でよいのだ。「ジコチューチョコ」。2021年はこの言葉だった、と筆者は考えている。(食の総合コンサルタント 小倉朋子)