酒類流通の未来を探る
酒類流通の未来を探る:小売最前線=限られた売場で選ぶ楽しみ
嗜好(しこう)の多様化を背景に、SM(食品スーパー)の酒類売場は品揃えの変化を続けている。市場の推移に合わせて缶チューハイなどのRTD売場が拡大、輸入ビールの棚は多くが国産クラフトビールに置き換わり、ウイスキーは輸入ブランドが増えた。ワインは広がった売場を維持、直輸入品や自然派ワインを打ち出す提案が増えている。バラエティーが必要な酒類売場は、スペースの制約やオペレーション負荷への対処が求められる。顧客にとっての選びやすさと管理の効率性を同時に追求し、食卓提案のキーカテゴリーとして売場の充実を目指す。(宮川耕平)
●増税と還元、影響は不透明
酒類は軽減税率の対象外なので基本的には駆け込み需要が発生するはずだが、店によってはキャッシュレス還元が実施されるため見通しは複雑になる。5%還元が適用される店の場合、実質的な購入金額は増税前より安くなる。そのため駆け込み需要はこれまでの増税時に比べ抑制されると思われるが、キャッシュレス決済の浸透度合いによっても結果は違ってくる。また、大手チェーンは還元支援の対象にならないため、駆け込みの獲得に取り組まない理由はない。
増税前後の動きは不透明でも、一定期間でならせばトントンになるという見方は多いが、それは総需要の話だ。
キャッシュレス還元によって消費者が利用する店を選別すれば、店舗間では格差が生じる。中小ストアの5%還元に対しては大手も何らかの対策を打つしかないので、価格競争やポイント付与合戦が激化するとの見通しもある。
還元支援策は10月から20年6月末まで実施される。この9ヵ月間の動向は、10月1日の前後にも増して不透明だ。また、キャッシュレス還元の効果が高いほど、制度が終わる7月以降の反動も懸念材料になる。
●均一価格が定番化
キャッシュレス還元の影響に関係なく、店舗で追求しなければならないのは店頭で選ぶ楽しさを提供しつつ、売場管理の効率を高めることだ。
品揃えの幅を広げることと、オペレーション負荷を抑制することは本来トレードオフの関係にあるが、酒類の嗜好は多様化しており単純な絞り込みでは顧客満足を得られない。かといって、人手不足のさなかに陳列業務を増やすことも難しい。
今年に入り、酒類のカテゴリーごとに均一価格を設定する店が増えている。狙いはチェーンによって異なる部分もあるが、選ぶ楽しさと管理効率を両立させる工夫という一面は共通している。
例えばビール類では、定番ブランドはジャンルごとに共通価格を設定し、限定品やプレミアムビールの一部は個別の売価設定とする場合が多い。
RTDでは定番ブランドを均一価格にするだけでなく、3本または4本の同時購入でさらに割引する提案が広がっている。ブランド指名買いのビールに比べ、RTDはその時々で選ぶフレーバーが変わり、ブランドスイッチも起こりやすい。自由な組み合わせでまとめ買いを促す施策は、RTDのニーズ特性にマッチし、買上点数のアップにもつながる。
価格を均一にすることで、カテゴリー内のさまざまな商品にトライしやすくなる。それがブランド単独ではなく、カテゴリーのファンづくりにつながる。イオンリカーは、この効果によって日本酒やウイスキーのファン育成に取り組む。同社はイオンリテールの100%子会社で、ワイン専門店の運営のほかGMS(総合スーパー)の酒類売場にも関わっている。
ウイスキーは980円均一のコーナーを導入、NBと直輸入品で構成する。需要期の12月をめどに、均一プライスを2980円、3980円と広げる計画だ。直輸入はスコッチから着手して各地域に拡大、品目に占める割合を現状の15%から来期には30%に高める。
日本酒も980円で大吟醸酒をコーナー化している。イオンリカーは各地の酒蔵との直取引を拡大中で、品揃えの充実を進めている。23年には日本酒の酒税が現在より17%ほど下がる。長期視点で伸長の余地があるカテゴリーと見ている。
●直輸入ワインが拡大
SMが取り組むメニュー提案との連動で、最も重視されている酒類はワインだ。食卓を華やかに演出するキーアイテムとして、関連販売の中軸に位置付けられることが多い。このワインカテゴリーであらためて直輸入ワインが拡大している。
直輸入ワインを強化する動きは、00年代の後半にも見られた。当時はイオンや西友、セブン&アイグループ、ドン・キホーテなどGMSが中心だった。現在、その取組みがSMにも広がっている。中でもヤオコーは輸入会社を設立し、低価格帯の補充にとどまらず、2000円台の高価格帯まで幅広く品揃えを拡充している。
直輸入品の高い粗利益率は、販促にも生きてくる。ヤオコーでは月に1日、ワイン全品2割引きセールを実施するが、直輸入品に関してはさらに1日、合計2日行う。また、7月には直輸入ワインの3割引きセールも実施した。直輸入品はワインの中核であるだけでなく、来店目的を作るカテゴリーと位置付けられている。
ワインの注目分野として、オーガニックなどの自然派ワインは着実に売場を広げている。イオンリカーで取り扱う自然派ワインは18年時点で約30品・売上構成比2%だったが、20年には100品、25年には200品に拡大、この時点で構成比30%を計画している。ここでも中心となるのは直輸入ワインだ。
環境やサステナビリティーに配慮した商品への関心は高まっており、酒類の中ではワインがこの分野における市場形成で先行している。こうしたところにもライフスタイル商品としてのワインの特徴が現れている。
●夕食シーンの獲得には酒類
店舗の新しい利用シーンを開拓する手段として、試飲コーナーや「ちょい飲み」機能を設ける売場づくりへの挑戦は続いている。酒類が主役のバー・スタイルだけでなく、酒類を脇役にする工夫もある。
8月末にリニューアルしたダイエー運営のイオンフードスタイル新松戸店(千葉県松戸市)は、「ちょいゴチ」の名称で食事を提供するコーナーを導入した。コンセプトは独自のブランド肉を使用したメニュー20種類を提供する「肉バル」で、このコーナーでは肉料理を引き立てるワインをセレクトして提供する。
外食需要を取り込む新たな機能への挑戦は、10月の消費税率アップによってどういった影響が出るか不透明な部分もある。短期的な懸念材料はあるものの、長期的に見て利用シーンの拡大はSMにとって不可欠の課題だ。
休憩シーンを獲得するためにカフェが必須の機能になったように、夕食需要を獲得する際には、ワインをはじめとする酒類の活用が重要になる。
-
◆酒類流通の未来を探る:新制度、難局面迎え正念場 次の一手に期待
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21●消費動向、不透明な一年 初夏の明るい雰囲気の中、「令和」への改元を迎えた19年。酒類業界では、日本酒を中心に改元記念商戦で予想以上のにぎわいをみせた。一方では「試練の年」とも言われる今年。市場環境を年間で考える場合、従来にも増して難しい局面を迎え…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:はせがわ酒店・長谷川浩一社長に聞く 酒のレベルは向上
酒類 特集 2019.09.21東京都内に複数店舗を展開し、酒の専門店として日本酒ファンから絶大な信頼を得ているはせがわ酒店。40年にわたり同社を率い、日本酒市場の拡大に力を注いできた長谷川浩一社長に、酒類業界の現状とこれからを聞いた。(丸山正和) ●「酒」のレベルは向上 適正価…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:酒類業界の平成を振り返る 規制緩和で競争激化
酒類 特集 2019.09.21平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:酒類の輸出入動向=輸出600億円突破 日本酒の海外展開…
酒類 特集 2019.09.21日本産酒類の需要が海外で高まっている。18年の輸出金額は約618億円と初めて600億円を突破。7年連続で過去最高を更新した。日本酒が成長をけん引する中、今後メーカーの海外展開が加速しそうだ。外需開拓が進む一方、国内の輸入酒市場は欧州産ワインの拡大に期待…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:ジェトロインタビュー=日本酒、海外ソムリエに照準
酒類 特集 2019.09.21日本産酒類のさらなる輸出拡大に向け、海外市場の開拓に積極的に取り組んでいるのが日本貿易振興機構(ジェトロ)だ。海外の酒類バイヤーと日本の酒類事業者とのマッチング支援に力を入れているが、日本酒についてはレストランに勤めるソムリエもターゲットに、焼酎・泡…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:イタリア大使館貿易促進部長に聞く 拡大期待のワイン市場
酒類 特集 2019.09.212月発効した日欧EPAにより、EU産ワインの関税はゼロとなった。これを契機にEU各国は、日本市場での販売拡大を目指し、さまざまな方策を練っている。欧州ワイン強国の一角を占めるイタリアワインについて、同国大使館貿易促進部のアリスティデ・マルテッリーニ部…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=国分グループ本社 「量から質」へ
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21国分グループ本社は「量から質」への転換を加速させて、大きな変革期を迎える酒類市場の課題解決を目指す。改正酒税法の順守を徹底しつつ、高付加価値の輸入酒や和酒の新しい飲み方を提案し、市場活性化に努める。酒類事業を統括する東野聡執行役員MD統括部長に、業界の…続きを読む
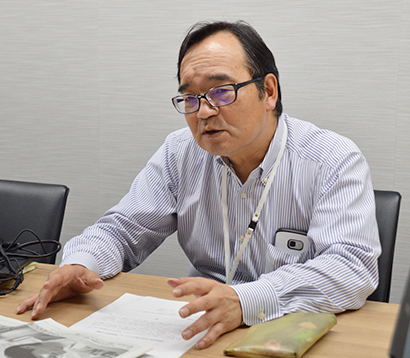
-
酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=日本酒類販売 変化対応へ柔軟な発想
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21日本酒類販売は、市場環境の変化に伴い消費者の購買行動が大きく変容する中、新たな需要創出に向け提案力を強化する。橋本則之専務取締役営業本部本部長は「固定観念に縛られては生き残れない」と指摘し、若者の嗜好の変化に対応するため、若手社員の柔軟な発想を生かし…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=三菱食品 生産性上げ競争力強化
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21三菱食品は今期、改正酒税法の順守を前提とした上で、サプライチェーン全体を俯瞰(ふかん)し、卸機能のレベル向上を図る。経営を効率化し生産性を上げることで、競争力アップに努める考えだ。同時に日欧EPA発効などで変化する市場に対応し、輸入ワインを中心にオリ…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=三井食品 「量より質」を継続強化
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21三井食品は、労働力不足による人件費や物流費の高騰に加え、酒類を取り巻く競争環境の厳しさを背景に、「量より質」の重点施策を継続的に強化する。メーカーコラボによる付加価値型のオリジナル商品戦略で差別優位性を高めるほか、物流受託の拡大などで反転攻勢に動く。…続きを読む
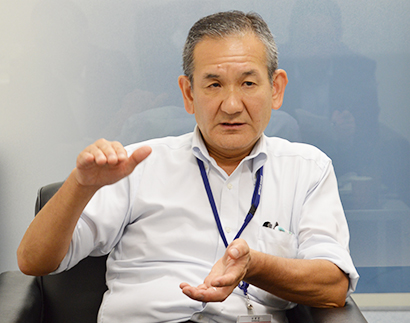
-
酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=伊藤忠食品 嗜好変化の対応が重要
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21伊藤忠食品は、10月の消費増税軽減税率制度施行に伴う酒類市場の先行きもにらみ、消費者の嗜好や購買行動の変化へ対応力をより高めていく。今期は既存顧客との取引深耕に加え、ドラッグストアやECといった成長業態や、業務用向けの取組みも強化する。角田憲治常務執…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=日本アクセス 酒卸にない提案目指す
酒類 特集 卸・商社 2019.09.21日本アクセスは、今年2年目となる中期経営計画で酒類と菓子の強化を掲げている。社内的には16年に酒類MD部を発足し、強みであるチルド物流網を生かした「生酒(なまざけ)」の提案に力を入れてきた。取り扱いの蔵元・アイテム数も着実に増えており、販売先も拡大中…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:イズミック・盛田宏社長 理念は得意先経営支援
酒類 特集 2019.09.21リテールサポート(得意先経営支援)を経営理念とするイズミック。今期は前期比1%増の2093億1900万円が目標。同社独自の切り口で情報発信を行う「イズミックマーケットアイ」は運用から1年が経過するなど、「価格競争から付加価値競争へ」に向けた取り組みを…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:名畑・名畑豊社長 足腰強い骨太企業体質へ
酒類 特集 2019.09.21外食文化発展のため、飲食店を総合的にサポートする関西最大手の業務用酒類食品卸・名畑。外食産業が直面するテーマに対して、積極的に解決策を打ち出す。社内では人事制度の全面改革に取り組む。今年からは飲酒運転撲滅活動を推進する「SDDプロジェクト」にも参画。…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:新潟酒販・雫石明社長 グループ力をフルに発揮
酒類 特集 2019.09.21新潟県で酒類卸を専業とする新潟酒販は、一昨年から国分グループとなり、新たなステージで独自の存在感を示している。新潟県は清酒88蔵と日本一の蔵数を誇り、県産酒は県外・海外への新たなビジネスを広げる柱だ。4月から新たに就任した雫石明社長は、「県産酒は強い…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:メーカーの視点から=サッポロビール・高島英也社長に聞く
酒類 特集 2019.09.21◇“四方よし”今後も追求 サッポロビールは創業以来、原料生産者との強い結びつきをもち、現在でも大麦とホップを自社で育種する世界で唯一のメーカーとして知られる。150年近い歴史を誇り、独自の文化をもつ同社の高島英也社長に、平成の振り返りと新たな令和時…続きを読む

-
酒類流通の未来を探る:小売最前線=限られた売場で選ぶ楽しみ
酒類 特集 2019.09.21嗜好(しこう)の多様化を背景に、SM(食品スーパー)の酒類売場は品揃えの変化を続けている。市場の推移に合わせて缶チューハイなどのRTD売場が拡大、輸入ビールの棚は多くが国産クラフトビールに置き換わり、ウイスキーは輸入ブランドが増えた。ワインは広がった売…続きを読む




















