新春特集第2部
新春特集第2部:2020年業界展望=食品卸売業 大きな試練の年に
いよいよ東京2020大会が開催される2020年は、食品卸業界にとっても大きな試練の年となりそうだ。インバウンドはじめ多くの需要出現の好機が見込める一方、首都圏で長期間実施される交通規制への物流対応、大会終了後の景気や需要の反動減など、山積みの課題へ直面する。6月のキャッシュレスポイント還元事業が終了以降、市場競争へいかなる影響を及ぼすかも不透明感が強い。少子高齢化と労働力不足が構造問題として重くのしかかる中、メーカーのリードタイム延長の急拡大やポイント還元事業に端を発する小売市場のデフレ競争再燃など、新たな難題が次々と待ち受ける。卸は変化対応業の本領発揮で相次ぐ課題を克服し、より的確な成長戦略を実行していくことが求められる。
●チャンスとピンチ混在
昨年の卸業界の動向を大手総合卸7社の18年度業績から見ると、日本アクセスを除く全社が増収で着地し、経常増益は一昨年同様の5社をキープした。コンビニエンスストア(CVS)やドラッグストア(DgS)をはじめとする有力チェーンとの取引拡大、各社が注力する低温関連事業などの伸長で規模拡大を継続しつつ、粗利の改善やコストの抑制に一定の成果を得た格好だ。ただ、物流費の増大で収益力の低下に歯止めがかからず、規模拡大に見合った利益水準への回復は足踏みを続けている。
総合商社系列の有力チェーンの取引集約や再編を含む小売業界の上位集約化などの動きに伴い、卸業界でも同様の構造が進む。18年度は加藤産業の大台突破で1兆円卸が4社となり、7社合計の売上高は9兆9065億円(前年比1.9%増)と10兆円に迫る勢いだ。
同年度に唯一0.3%の微減収となった日本アクセスはファミリーマートの統合による店舗減で構成比29%を占めるCVSが3.4%減となったためだが、最大構成比のリージョナル食品スーパー(SM)をはじめナショナルチェーンやDgSなど他の業態は前年実績を超えた。経常増益となったのは三菱食品、日本アクセス、国分グループ本社、加藤産業、三井食品。深刻な人手不足による物流費の上昇が続く中、各社ともRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用による事務コストの削減、得意先小売業に物流サービスレベルの緩和などを交渉し、販管費の低減に努めている。
一方で価格より機能が優先される低温領域への対応強化などで粗利の改善に努め、18年度は増益基調を維持した格好だ。ただ、販管費の最大構成比を占める物流コストの抑制には苦慮しており、粗利の改善成果を相殺される構造が続く。18年度に経常利益率1%を超えたのは、引き続き加藤産業のみとなった。改正酒税法施行による収益改善効果も含め、経常利益率1.14%の高数値を確保した。他の大手卸では日本アクセスが0.92%と1%へ最も近い距離にあるが、7社平均の経常利益率は0.72%と、前年より0.01ポイントの後退を強いられる厳しい情勢だ。
昨年はわが国にとって改元の節目であり、これに伴う酒類など関連商品の特需も一部発生。5月の異例のゴールデンウイーク10連休は物流問題も懸念されたが、大きな混乱もなく乗り越えた様子。9月には消費増税前の駆け込み需要が酒類を中心に発生、ラグビーワールドカップ(W杯)の全国的な開催で飲食需要も活気づくなど、消費面ではいくつかの好材料にも恵まれた。
ところが、そうしたプラス要素をあっけなく吹き飛ばすようなコスト環境の悪化に業界は苦慮している。20年3月期の大手全国卸4社の第2四半期業績(19年4~9月)は増大する販管費を吸収しきれず、2桁台の大幅減益を強いられた企業も目立つ。
各社の上期業績における販管費率の状況を見ると、三菱食品(0.03ポイント減/6.29%)、三井食品(0.13ポイント増/9.08%)、伊藤忠食品(0.04ポイント増/4.83%)。日本アクセスは販管費率は非公表だが、額では前期比1.3%増としており、総体的にコスト環境が悪化。その背景にあるのは、いうまでもなく昨今の労働力不足による配送費や庫内費など物流コストの高騰だ。
三菱食品は上期の自社物流費に関しては計画通りに下げたため販管費率は改善したが、得意先専用拠点向けのセンターフィー上昇による売上原価の増加を受け、営業減益を強いられた。
日本アクセスも上期は、物流のBPI管理の徹底や得意先チェーンとの配送頻度の最適化などで改善成果は得たものの、それを上回る物流事業者からの値上げを吸収しきれない状況だ。
三井食品は増収に伴う物流経費の大幅な増加が収益に影響。伊藤忠食品は夏場の天候不順や一部帳合変更の影響で減収となり、売上総利益率・販管費率とも前年比では悪化した。ただ、いずれも想定内の数値に収めたことで、上期は利益面では計画を上回る着地となった。
一向に歯止めがかからないコスト環境の悪化に対し、各社とも下半期の重点課題に物流費の抑制を挙げる。庫内作業の省人化・自動化など最新テクノロジーを活用した個社の努力に加え、同業間での共同配送など業界連携による物流合理化を模索していく。
●メーカーのリードタイム延長が負担増に
一方で昨年来、メーカー間で卸への納品リードタイム延長(受注翌日納品→受注翌々日納品)の動きが広がるなど、川中の業務負荷が増大する要素が表面化。リードタイムの延長は卸に在庫の積み増しや倉出し物流の増加といったコスト負担をもたらすため、「数年前にあるNBメーカーが(受注翌々日納品について)言っていた時は、そんな動きもあるのかという程度に受け止めていたが、今は大手から中小へ一気に増え、在庫の持ち方が変わりコスト上昇に苦慮」(地域卸)、「これまで生産性の改善を第一にコストを抑えてきたが、リードタイム延長で在庫が増え、生産性が大きく悪化。物流費だけでなく庫内費もアップしている。物流費が上がっているのはメーカーだけではないのに」(大手卸)といった不満も聞こえてくる。
卸は在庫の積み増しへ拠点の増床なども検討しなければならない局面にあるが、リードタイムを延長してもASN(事前出荷情報)の活用で検品レスを実践し、卸拠点への入荷業務を顕著に合理化した先行大手NBの成果事例もある。
こうした情勢を受け、昨年は日本加工食品卸協会(日食協)がリードタイム延長に伴う業務合理化への要望書をメーカー・小売業へ提出する動きも。今後、この問題を前進させるにはメーカーから卸への入荷をより効率化できる仕組みを整備するとともに、卸から小売業への納品回数や納入時間・形態といった物流与件の緩和も含め、サプライチェーン全体で議論・取り組むスタンスが不可欠だ。
●五輪伴う交通規制対応急務 継続的成長へ問われる戦略
今年の食品業界における最大のヤマ場は、7~9月に開催される東京2020大会に尽きるだろう。大会期間中および前後は世界各国から約4000万人が訪日するとみられ、インバウンド需要をはじめ競技場・家庭内での観戦需要など、多様なシーンで酒類や飲食料品の消費が増えると想定される。
一方で大会期間中の円滑な車両移動などを目的に、首都圏の26大会競技場・20エリアで大規模な交通規制が実施される。競技場の集中する首都圏臨海部にはメーカーの低温拠点が数多く存在する上、都内には路面店のSMやCVSも多く、卸がこれらの店舗へ平常通りに商品供給できるか、懸念材料となっている。
日食協は卸各社がメーカー・小売業と商品仕入れや店舗納品に関わるBCP(事業継続計画)を策定すべく呼びかけを強化しており、大会開催まで7ヵ月を切った現在、早期に対応を進めることが重要な局面だ。
大会直前の6月にはキャッシュレスポイント還元事業が終了し、政府がマイナンバーポイントをはじめ、追加施策も視野に入れているが、現状ではその効果は不透明。秋以降は大会終了による需要の反動減、ポイント還元効果の消失による消費の冷え込みも想定され、食品流通がより過酷な体力勝負へ突入していくことも懸念される。
こうした環境与件をしのぎつつ、卸業界が継続的成長を果たすために、個々の戦略のあり方も問われる一年となりそうだ。物流費の上昇と小売業の見積もり合わせの増加を背景に、既存卸事業を取り巻く収益環境は厳しさを増している。
少子高齢化や人口減少、変わり続ける生活者のライフスタイル、ネットとリアルの融合といった市場の変化を的確に捉えて、新たなビジネスモデルを構築することが求められる。
三菱食品がネットとリアルの融合、キャッシュレス社会の進展を見据えて小売業へ提案する「日本型ニューリテール」、伊藤忠食品が今年からの5G(第5世代移動通信)提供開始で変わる市場を捉えた動画メディアとの提携戦略など、川中発の新たな事業モデルも登場してきた。
日本アクセスが高度な情報卸構想を打ち出す一方、伝統的な乾物メーカーを組織化(AK研)してネットや外食などの販路拡大に乗り出した試みも付加価値性がある。
今年で推進中の第10次長計が終了する国分グループ本社は同計画で地域密着と低温対応に成果を示し、大規模3温度帯拠点の全国配備を完了。昨年のラグビーW杯ではこの機能が評価され、全国の競技場へ酒類を供給する役割を果たした。東京2020大会の成功に向けても、卸の任務を全うしたい考えだ。
加藤産業は国内の人口減少に対応し、海外戦略を積極化している。昨年12月にはマレーシアで新たに現地企業を買収し、同国最大の卸グループ基盤を確立。今後、海外の各拠点を利用してASEANを面で押さえる戦略を展開するという。
三井食品は下期の重点として「卸としての原点回帰」(基本の徹底)へ努めつつ、魅力ある商品を売り込む卸の本業を重視。特に輸入酒類などで高い実績も持つため、グローバル対応の強化によって商品施策における独自色をより強固に打ち出したい狙い。
トモシアホールディングスは産学連携やエリアの中小零細顧客への商品供給の継続など「地域」に軸足を据えた生き方をより鮮明に追求。併せて競合大手が採算性などから手の出せない外食市場や製造分野を深耕し、独自の成長領域に位置付ける。昨年12月にはベトナムで水産加工を行う関係会社の新工場も竣工し、業務用向けなどに供給力を強化。既存卸事業の規模は維持しながら全体利益の底上げに寄与させていく。
(篠田博一)
-
◆新春特集第2部:中小企業の底力 “匠の味”を世界へ
特集 総合 2020.01.03南北に長く、周囲を海に囲まれた日本には四季がある。各地域には風土やそこに住む人たちの嗜好(しこう)に則した地場産品・郷土料理があり、これら“匠の味”を守る中小規模の食品メーカーが多数存在する。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控…続きを読む

-
新春特集第2部:2020年業界展望=食品卸売業 大きな試練の年に
特集 卸・商社 2020.01.03いよいよ東京2020大会が開催される2020年は、食品卸業界にとっても大きな試練の年となりそうだ。インバウンドはじめ多くの需要出現の好機が見込める一方、首都圏で長期間実施される交通規制への物流対応、大会終了後の景気や需要の反動減など、山積みの課題へ直面…続きを読む
-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=日本アクセス・佐々木淳一社長
特集 卸・商社 2020.01.03日本アクセスは今年、第7次中計の最終年度を迎える。売上げ拡大が難しい環境下、経営の中身を変え利益率1%確保、利益額で食品卸ナンバーワンを目指す。まいた種が徐々に結実しており、提案機能をさらに磨く。新たなビジネスモデル構築にも着手するなど、筋肉質の経営…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=三菱食品・森山透社長
特集 卸・商社 2020.01.03「食品流通には多くの無理・無駄・ムラがあり、ここに手を打ってこそ、現状をブレークスルーできる」。三菱食品の森山透社長は現状認識を示し、自らの体質強化と並行して、サプライチェーン全体を視野に経営改革を加速。5月には本社移転も控え、新たな展望の開ける年に…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=国分グループ本社・國分晃社長
特集 卸・商社 2020.01.03国分グループ本社は今年、推進中の第10次長期経営計画(16~20年度)の最終年を迎える。業界構造の変化に適応しつつ、社内の意識改革を含め各種施策を加速。目標の達成と長計の総仕上げに力を注ぐ。國分晃社長に展望を聞いた。 ●10次長計、総仕上げへ 目標…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=伊藤忠食品・岡本均社長
特集 卸・商社 2020.01.03伊藤忠食品は今期、中核である卸事業の基礎収益力アップを最優先に掲げる。社長就任以来力を注ぐ事業領域の拡大については、パートナー企業との連携強化を通じたシナジーの発揮に努めていく考えだ。岡本均社長に20年の業界展望や抱負を聞いた。 ●収益力アップを最…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=三井食品・萩原伸一社長
特集 卸・商社 2020.01.03三井食品の萩原伸一社長は20年の経営環境は極めて不透明感が強いとし、自社の重点戦略として「基本の徹底」を加速する。経営の無駄の削減や物流効率化の追求で体質改善を進めつつ、AI(人工知能)やグローバル対応を軸に企業付加価値の向上にも挑む。萩原社長に展望…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=加藤産業・加藤和弥社長
特集 卸・商社 2020.01.0319年9月期連結業績は売上高が2年連続で大台の1兆円突破となり、経常利益は7年ぶりに過去最高を記録し、増収増益で着地した加藤産業。グループの成長戦略の一つと位置付ける海外事業も着実に推進し、成果を挙げている。加藤和弥社長に今後の展望を聞いた。 ●利…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=トモシアHD・竹内成雄社長
特集 卸・商社 2020.01.03トモシアホールディングスの竹内成雄社長は市場の競争やコスト環境が一段と厳しさを増す中、企業理念でもある「地域市場への貢献」を軸に競合との差別化を図る構えだ。並行して企業体質の強化・成長分野への投資を加速し、独自の事業モデルを築く。今後の戦略を聞いた。…続きを読む
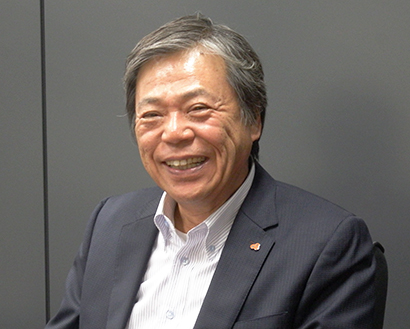
-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=日本酒類販売・田中正昭社長
特集 卸・商社 2020.01.03「東京オリンピック・パラリンピックは日本酒を世界に知ってもらう絶好の機会」と語るのは日本酒類販売の田中正昭社長。全国に広がるネットワークを生かし、商品発掘や蔵元巡りなどのコト提案に卸の立場から力を注ぐ考えだ。田中社長に20年の展望や戦略を聞いた。 …続きを読む

-
新春特集第2部:2020年業界展望=業務用食品卸 生鮮・素材が差別化の鍵
特集 卸・商社 2020.01.0319年は、2月・関東食糧(埼玉県)が新物流センター「食空間創造Base」竣工、4月・日本外食流通サービス協会(JFSA)に首都圏初の会員として久世(東京都)が加入、11月・ニッカネ(栃木県)が西東京営業所を開設したことなどが主立った動きだった。北関東で…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=トーホー・古賀裕之社長
特集 卸・商社 2020.01.03トーホーが3ヵ年中計を折り返した。前半は収益確保に苦しむも内外のM&A(企業の合併・買収)と既存社で事業基盤を拡大。業務用食品卸事業(DTB+C&C)で売上げ2000億円突破も見えた最終年度は全28社で収益力向上、グループ連携強化、海外事業力強化に継…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=尾家産業・尾家啓二社長
特集 卸・商社 2020.01.03尾家産業は今期、若手幹部主導で策定した新中計を始動した。売上高1000億円突破で締めくくった前中計から一転、今中計は開始時から大口取引終了や物流コスト増大、経費先行型経営の改革など課題が山積。全体最適で変革に挑み、次ステージへの地盤を固めている。 …続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ヤグチ・栗栖信也社長
特集 卸・商社 2020.01.03ヤグチの前5月期業績は、売上高は前年比0.5%増の774億4500万円と新規取引拡大などにより微増収だったが、利益は物流費・人件費の増加で減収。栗栖信也社長に10月からの軽減税率の影響、20年の東京オリンピック・パラリンピックへの期待などについて聞い…続きを読む

-
新春特集第2部:2020年業界展望=中食 照準絞り潜在能力高める
特集 中食 2020.01.03食産業は、少子高齢化などの人口構成の変化やライフスタイルの多様化、働き方改革の推進などに加えて食の外部化の進展により大きく変わりつつある。人口の減少は、食にとっては将来的に減少要因となっているが、現在の内食、中食、外食の合計支出額である食全体のマーケ…続きを読む

-
新春特集第2部:2020年業界展望=スーパー 増税・還元支援の衝撃
特集 小売 2020.01.03◇全国規模で再編促す 2019年は全国の食品スーパー(SM)で経営体制を見直す動きが広がった。方向性は大きく二つ。一つは政府のキャッシュレス・ポイント還元事業に合わせて減資する企業が増えたことだ。多くの経営判断が示したように、政府資金による5%還元支援…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=サミット・竹野浩樹社長
特集 小売 2020.01.03サミットは20年度から新中期3ヵ年経営計画をスタートさせ食を起点に社会課題を解決できる食品スーパー(SM)としてコミュニティーの場となる店づくりを追求する。商品は生鮮の惣菜化など即食商品を強化しカテゴリーも広げる。小型店の開発も進め都心で店舗網を構築…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ライフコーポレーション・岩崎高治…
特集 小売 2020.01.03ライフコーポレーションの岩崎高治社長は、幹部からパートスタッフに至る意識改革の進捗(しんちょく)に自信を示す。20年度の課題は、店づくりや販促策の個店対応を一段と深掘りしていくことだ。また、アマゾンとの協業によるネット販売エリアを東京23区全域や大阪…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=全日食チェーン 平野実・全日本食…
特集 小売 2020.01.03◇全日食チェーン 平野実・全日本食品社長 全日食チェーン(本部=全日本食品)は20年度、商品力の強化に重点を置く。低温度帯商品を充実するため、投資をかけて商品供給などインフラを整え、売場づくりも支援する。加盟店支援のリテールサポート(RS)も体制を…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=セルコチェーン・佐伯行彦理事長
特集 小売 2020.01.03セルコチェーンの佐伯行彦理事長(さえきセルバホールディングス〈HD〉社長)は、ボランタリーチェーン(VC)の役割も変化が必要と指摘。19年は店長などの教育カリキュラムを刷新、外国人技能実習生の管理団体も設立した。管理業務の共有化やネット販売の構築も課…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=日本生協連・嶋田裕之代表理事専務
特集 小売 2020.01.03日本生活協同組合連合会(日本生協連)は厳しい経営状況を改善するため、1月に宅配のリノベーション(業態革新)に向けた新たな組織を設置する。また、SDGs(持続可能な開発目標)への対応を進めるため、倫理的(エシカル)消費に対応する商品開発を進める。 ●…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=コープデリ生協連・土屋敏夫代表理…
特集 小売 2020.01.03コープみらいが加盟するコープデリ生活協同組合連合会は2020年、第3期中期計画の初年度で、成長軌道を取り戻すための変革期に入る年と位置付ける。慢性的な人手不足を前提とした省人化・効率化を進めつつ、地域密着の食品の開発など組合員に寄り添って活動する。 …続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=パルシステム生協連・大信政一代表…
特集 小売 2020.01.03◇パルシステム生活協同組合連合会・大信政一代表理事理事長 関東甲越などの中堅生協が参加するパルシステム生活協同組合連合会は国産品を中心に独自の商品を展開して、産地と組合員の交流を図ってきたが、この活動を2020年以降、さらに強化していく。今年の総会…続きを読む

-
新春特集第2部:2020年業界展望=CVS 脱一律、ビジネスモデル転換へ正念…
特集 小売 2020.01.03コンビニエンスストア(CVS)業界は24時間営業を基本とした店舗運営や品揃え、加盟店指導、組織体制を見直し、ビジネスモデルを転換できるかが問われる。2019年、加盟店の人手不足は深刻で社会問題視され、国も対策に乗り出し、各チェーンが行動計画を求められる…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ローソン・竹増貞信社長
特集 小売 2020.01.03ローソンは加盟店に寄り添ったコンビニエンスストア(CVS)経営を推進する。全国一律の店づくりから脱却し、地域や立地に応じて消費者のニーズに対応する。積極的に社会の声も聞いて自らの変化を促し、デジタル技術と融合させた新しい付加価値ある店づくりを目指す。…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ファミリーマート・澤田貴司社長
特集 小売 2020.01.03ファミリーマートは加盟店との信頼関係を強固にして、地域に根差したコンビニエンスストア(CVS)を目指す。いち早く情報を共有して迅速に課題解決し、本部の店舗指導員も職住近接で加盟店に密着しながら運営を支援していく。既存店の客数を重視し、着実な成長を図る…続きを読む

-
新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ミニストップ・藤本明裕社長
特集 小売 2020.01.03ミニストップは21年度の施行を目指しフランチャイズパッケージを改革する。売上総利益にロイヤルティー率を適用する現行モデルから店舗の営業利益を本部と加盟店が分配するモデルへ転換、ビジネスの構造を作り変える。共通の目標でベクトルを合わせるという。 ●事…続きを読む

-
新春特集第2部:2020年業界展望=DgS ヘルスケア重視・食補完が優位
特集 小売 2020.01.03上場ドラッグストア(DgS)企業の既存店営業成績を売上高前年同月増減率で確認してみると、消費増税前の19年9月に20%増以上のプラス実績も多いが、10月に大幅な減少もある。増税前の駆け込み需要は往々にして需要創造ではなく、需要の先取りにすぎないケースが…続きを読む

-
新春特集第2部:2020年食品界経営者・有識者アンケート(1)
特集 総合 2020.01.03◆社会変化に危機意識 顧客・取引先を重視 日本食糧新聞社・日食動向調査室が19年11月中旬から12月前半に掛けて実施した食品界経営者・有識者アンケートからは、社会の変化を実感するからこそ、顧客や取引先などステークホルダーとの関係を重視したいという傾…続きを読む
-
新春特集第2部:2020年食品界経営者・有識者アンケート(2)
特集 総合 2020.01.03〈アンケート概要〉 (1)20年の食品界に大きな影響を与える、または動向の鍵を握ると思われる言葉(キーワード)を選び、その言葉を選んだ理由。 (2)食の安全・安心の確立・徹底・深化に向けた取組みに対し、消費者からの理解を得る上で、鍵を握ると思われ…続きを読む

















