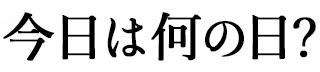
野菜が不足気味なときに活用したい野菜ジュース 野菜飲料には、トマトやニンジン、パンプキンなどの単品の野菜を原料にしたジュースおよびドリンクと、トマトやニンジン、セロリ、クレソン、ビート、ビーマン、ほうれん草、キャベツ、レタス、パセリなどの野菜を混合使用…続きを読む
野菜や穀類よりも肉類に近い組成の大豆 日本食品標準成分表2010による大豆の主要成分は、たん白質35%、炭水化物28%、脂質19%、 水分13%、灰分5%となっている。たん白質のアミノ酸含有量およびその組成は、ほかの野菜や穀類に比べると、きわめて肉類に…続きを読む
ところてんから発明された寒天 トコロテンは遣唐使によって1000~1200年前に伝来し、鎌倉時代(1192~1333年)にはすでに京都で心太座(トロコテン店)が開かれていたとの記録も残っている。このトコロテンから乾燥品である寒天を発明し、その卓見により…続きを読む
逸話が多いレーズン 紀元前のはるか昔に、ぶどう畑で自然に乾燥された一粒のぶどうがたまたま偶然に発見されたものが人類が初めてみたレーズンと考えられている。 紀元前1490年に、「レーズンはぶどうを天日乾燥したものである」との記述があると歴史書が記している…続きを読む
梅干しは素材の風味を生かした漬物 野菜に食塩をまぶしたり、野菜を食塩水に浸けると浸透圧により、野菜組織がしんなりして食べやすくなるとともに酵素の働きにより風味成分が形成されて、漬物特有の味が出てくる。さらに乳酸菌や酵母によって発酵風味が加わる漬物もある…続きを読む
コラーゲンたっぷり、豚足 【猪脚 zhūjiáo 別称 猪蹄 zhū ti】 ひづめのついた足首の部分。骨と爪以外の皮や肉、軟骨などを食べる。毛が残っている場合は剃ったり、抜いたりしておくと舌ざわりがよくなる。コラーゲンやエラスチンなどのゼラチン質を多…続きを読む
プレミックスが販売され、子供のおやつとして定着したホットケーキ 1931(昭和6)年に、ホーム食品が発売した商標名「ホームラック」商品名「ホットケーキの素(無糖)」がプレミックス第1号である。その後、第二次世界大戦で異常な食糧危機になるが、1952(昭…続きを読む
日本におけるビールの個人消費は、所得倍増の波に乗って 戦後の混乱のなかでビール会社は復興への努力を開始した。 1949年、ビール産業にも過渡経済力集中排除法が適用され、トップメーカーである大日本麦酒が2分割されて戦後の新しい体制ができあがるとともに、酒…続きを読む
神話にも登場するアーモンド 人類は古くからアーモンドを栽培していたとみられ、紀元前3200年ごろのヨルダンの首都アンマン南西部の遺跡でアーモンドの殻が発見されている。紀元前1500年頃の地中海東岸を中心にした古代オリエント世界では、香辛料、蜜、没薬など…続きを読む
インドに「カレー」はない 今日、わが国で「国民食」とよばれて親しまれている料理がカレーであるが、その基本にあるのがカレー粉である(今日業界で「即席カレー」に対して単 に「カレー粉」あるいは「純カレー」とよんでいる)。 カレー粉は種々の香辛料(スパイス)…続きを読む
オムレツに欠かせないケチャップの歩みは、トマト栽培の歩みとともに トマト加工は、1876(明治9)年にアメリカから帰国した大藤松五郎氏が内務省新宿試験場において、トマト缶詰の加工実験を行うなど、農事試験場などで は実験的なことが早くから行われていた。 …続きを読む
江戸時代中頃から始まったぬか漬け 野菜などをそのまま、または前処理した後、ぬかを主とした材料に漬け込んだものをいい、代表的なものがたくあん漬である。 たくあん漬の名称は、沢庵和尚が始めたからという説、沢庵和尚の墓石が漬物石に似ているからという説、大根の…続きを読む
国内のすべての牛には個別識別番号がある わが国では、食肉のJAS規格といわれるトレーサビリティと、食肉の品質などを判定する格付制度により、牛と豚などの食肉の安全性を確保している。 トレーサビリティとは、国内のすべての牛、生体で輸入された牛に10ケタの個…続きを読む
年中美味しく食べられるホタテ缶 ホタテ貝缶詰の原料には、北海道と東北地方で養殖されたものが使われている。ほとんどが「水煮」缶詰だが、若干量の「味付」缶詰も流通している。「水煮」には、外套膜(がいとうまく)を取り外し、貝柱が丸のままの形(ホール)になった…続きを読む
おむすびの人気の具材は、梅や鮭、そしてツナマヨネーズ。「ツナ」にはカツオも含まれる マグロ類とカツオの缶詰は総称し て「ツナ缶詰」といわれる。原料魚種別では肉色が白いビンナガマグロを使用した「ホワイトミート」と、魚肉が淡紅色のキハダ・メバチ・カツオを使…続きを読む
禁酒法の時代に生産量を伸ばしたカナダのウイスキー アメリカンウイスキーはスコットランドやアイルランドからの移民が、土地に産する穀類から蒸溜酒を作ったことが始まり。初めはライ麦が主要な原料とな った。1775年に始まった独立戦争後にはウイスキーに重税がか…続きを読む
殺菌剤、合成保存料を添加せずとも長期保存ができるレトルト食品 レトルト食品は、食品を容器に詰め、外から細菌が浸入できないように密封した後、100℃以上の高温で殺菌して容器内食品に付着した細菌を殺滅している。この製造過程は缶詰とあまり変わりがない。違いは…続きを読む
鏡餅をかき砕いて作った「おかき」 もち米を原料として作られた 米菓を「あられ」「おかき」という。それぞれの名称の起源については以下のようである。「あられ」については、ひな祭 りに供えられる「ひなあられ」はもち米製品であり、また、寒い時に降る「霰(あられ…続きを読む
またの名をプルマンブレッド 角形食パン(プルマンブレッド) 三斤サイズのパン型に生地を詰め、蓋をして焼成することによって角形に焼き上げられる。一斤とは約1ポンド(450g)の生地重量を使用したパンのサイズをいう。二斤サイズ、あるいは一斤サイズのパン型を…続きを読む
鹿児島の名産品、芋焼酎 さつまいもを二次の掛原料に使用したもの。主産地は鹿児島県、宮崎県南部である。いもはコガネセンガンが多く洗浄後両端および線虫、黒斑病による病害部を完全に切除し、製品にヤニ臭、線虫臭、黒斑病臭のつくのを防ぐ。一次モロミは麹米100k…続きを読む
神父が作ったマカロニ工場 日本で初めてパスタが作られたのは1883(明治16)年頃、フランス人宣教師マルク・マリ・ド・ロ神父が、長崎県長崎市外海町に煉瓦造・平屋建のマカロニ工場を建設し、製造したのが最初であるといわれている。1945(昭和20)年代まで…続きを読む
精進料理の大将として描かれた糸引き納豆 納豆発祥の地は、はっきりしていない。各地に納豆発祥伝説がある。 源義家が戦地で農民に馬の餌を求めたところ、俵などに詰めた煮豆をさし出し、数日後、この煮豆が納豆になっていたという説、朝鮮に出兵した、加藤清正が、馬の…続きを読む
美味しいコーヒーを煎れるには、豆の選別や包装の工程も気が抜けない レギュラーコーヒーの製造工程としては、原料生豆の工場搬入から製品の出荷まで4工程に大別することができる。まず生豆に混入している夾雑物や不良豆を取り除く選別工程があるが、発酵したりカビが生…続きを読む
ドーナッツにはアメリカンタイプ、イングリッシュタイプ、フレンチタイプの3種がある アメリカンタイプは混合生地を展延、型抜きして油揚げ、イングリッシュタイプは混合生地を発酵させ、ガス抜き、ふ抜きを十分行って型抜き、ホイロどりして油揚げする。フレンチタイプ…続きを読む
スープを意味していた羹は、やがて和菓子へと変化した 羹に多くの種類があり、室町時代の『庭訓往来』などには白魚羹・鼈羹・海老羹・猪羹・羊羮ほか多くの名前が記されている。羹は中国では、スープとして食べられており、羊羮は羊の肉を使ったスープであった。 羹をも…続きを読む
世界で最も使われている着色料、カラメル カラメルは食用糖類の加熱処理物であるが、加熱処理の度合と利用法により、食品として扱われるものと食品添加物として扱われるものに大別される。 カラメルがいつ頃から利用されるようになったかは明らかではないが、ヨーロッパ…続きを読む
トロの美味しさは脂肪分によるものだけではない 油脂の特性として、単独で食べても美味しさは感じないものの、ほかの食品成分の旨味を引きだす大切な役割がある。マグロのトロや霜降り牛肉の美味しさは、 たん白質と油脂の組み合わせによるものである。 (日本食糧新聞…続きを読む
熱した石の上で作られた無発酵パン パンは人類にとってきわめて伝統的な食品であり、約6000年前のチグリスユーフラテス河畔では小麦粉粥を熱した石の上で焼いた無発酵パンが食べられていたと推察されている。このようなパンが中近東諸国では今日でも継承されている。…続きを読む
稲作の神様が宿る鏡餅 わが国の稲作が始まったのは縄文時代で、本格化したのは弥生時代。稲作の普及を機に社会が格段に変化した。すなわち日本文化は、稲を主軸とした農業 文化により開花したといっても過言ではない。水田が日本を代表する光景であり、田植えや稲刈りな…続きを読む
もちを正月に食べるようになったのは徳川の時代になってから “もち”そのものは歴史が古く、 縄文時代からあったといわれている。しかし、その時代は雑穀の粉を水でこね、蒸上げて搗(つ)いたもので、“もちひ”と いわれるものであったという。 歴史上“つきもち”…続きを読む
「まめに働く」ことを願う黒豆は、身体に良い黒大豆 「黒大豆」は正月料理に使う黒豆に利用されている。利用上からは、一般加工用、煮豆用、枝豆用、油脂原料用ならびに緑肥、飼料用などに分類されている。 日本食品標準成分表2010による大豆の主要成分は、たん白質…続きを読む